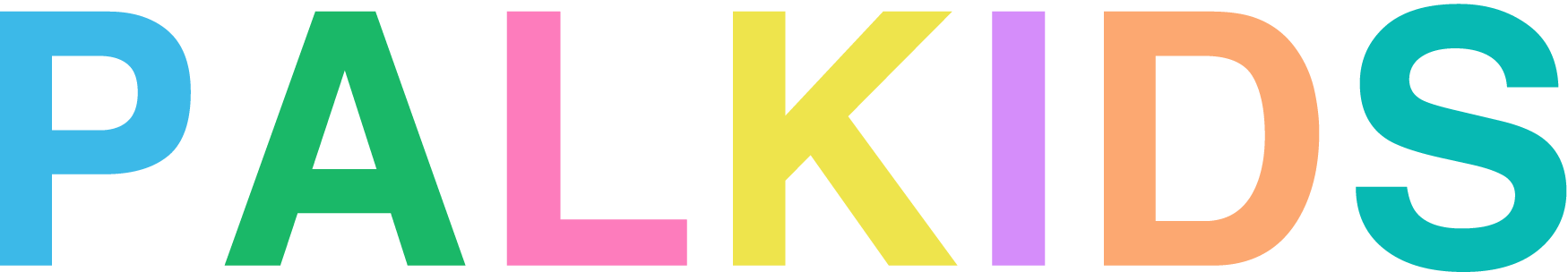パルキッズ通信 特集 | 大量インプット, 言語学, 言語獲得
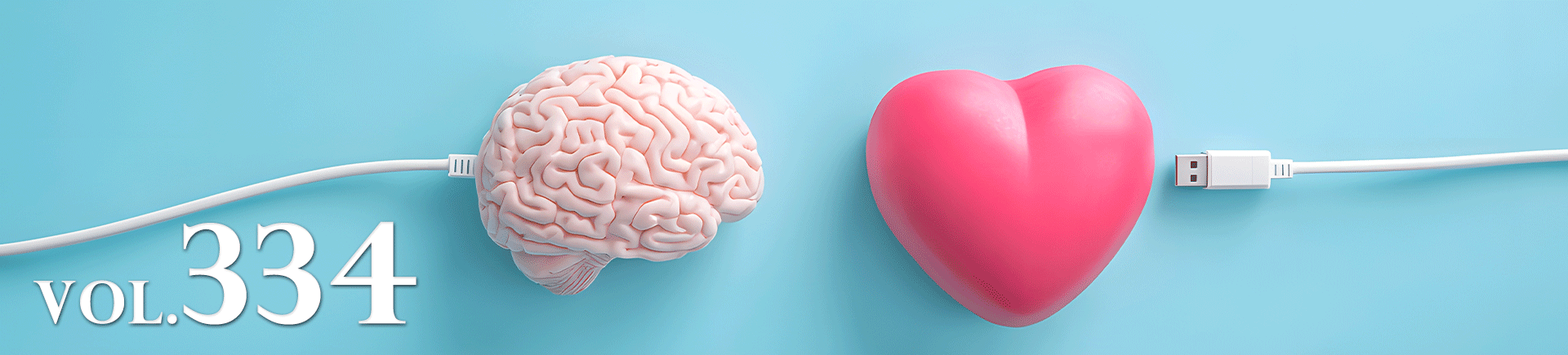
2026年1月号特集
Vol.334 |「インプット」だけ、あとは子どもの脳に任せる英語教育
カテゴリー構築から心内辞書の充実、高い理解力まで
written by 船津 洋(Hiroshi Funatsu)
※本記事のテキストは引用・転載可能です。引用・転載する場合は出典として下記の情報を併記してください。
引用・転載元:
https://www.palkids.co.jp/palkids-webmagazine/tokushu-2601/
船津洋『「インプット」だけ、あとは子どもの脳に任せる英語教育』(株式会社 児童英語研究所、2026年)
分けることから始まる言葉の世界
 ヒトは進化の過程で、様々な音声を発するのに都合の良い体の構造を手に入れました。具体的には、肺からの呼気が声門を震わせて作られる音源を、咽頭から口腔、あるいは鼻腔などの空間、さらには歯や唇などの障害物を利用して、多種多様な音声として発することができます。ヒトの他にも、サルやイルカなど音声を発してコミュニケートする動物はいますが、我々ヒトが発するほどのバリエーションを持った音声は類がないでしょう。これは我々の先祖が、言語を発達させるうえでの福音でした。
ヒトは進化の過程で、様々な音声を発するのに都合の良い体の構造を手に入れました。具体的には、肺からの呼気が声門を震わせて作られる音源を、咽頭から口腔、あるいは鼻腔などの空間、さらには歯や唇などの障害物を利用して、多種多様な音声として発することができます。ヒトの他にも、サルやイルカなど音声を発してコミュニケートする動物はいますが、我々ヒトが発するほどのバリエーションを持った音声は類がないでしょう。これは我々の先祖が、言語を発達させるうえでの福音でした。
このように音声の調音に適した器官を持ったことで、言語を発達させるベースができました。同時に、概念化という能力も身につけています。概念化とは、世界から対象を切り出す能力のことです。「水、山、家、服」などの物の名前は概念ですし、「走る、寝る、食べる」などの動作も概念です。また、形容詞や副詞も概念です。これらを世界から切り出して、ひとつの範囲(景色から川を特定するなど)を決めてそれを共有することで、コミュニケーションが成立するようになります。この概念化の能力も、音声調音の能力と合わせて、言語発達の下地を構成します。
ここまでは、ヒト以外の生物でも能力として持っています。サルやイルカ、あるいは鳥なども概念と音声でコミュニケートします。
ただし、ここからがヒト特有です。「離散無限性」と言われますが、ヒトの言語では音素を組み合わせて語をつくり、語を組み合わせて句を作ることができます。日本語でも、次々と新語が作られますが、音素を組み合わせて、さらに音節を組み合わせることで、作ろうと思えばいくらでも新しい音声を生み出すことができます。また、そのようにして生み出された語を組み合わせて、これまた無限に文を生み出すことができるのです。この後半部分の、語を組み合わせて文を作る部分を担うのが文法の能力です。この文法能力こそが、ヒトの言語が他の種の概念・音声を使用したコミュニケーションと一線を画すところです。
これら、音声調音・概念化・文法能力の3つの能力を、我々は日常的に使用して生活していますが、日常使いにおいては、これらの能力を有していることに気づくことはありません。人の話を聞き取って、その意味を心内表象する、あるいは理解する作業も、我々は幼児期に身につけてしまっていています。どのように身につけたのかは覚えていませんが、母語を使いこなすことはどんなヒトにも共通しています。加えて、その言語使用は「手続き記憶」になっているので、自転車と同じで「一度身につけてしまえば、息をするようにできてしまう」そんな能力なのです。
さて、ここまでヒトの言語使用について見てきましたが、問題は、我々日本人にとっての英語です。英語を身につける日本人は数多ありますが、同時に英語を身につけられない日本人もそれ以上に存在します。そして、本誌をお読みの皆様は、「我が子には英語を」と願っていらっしゃるはずです。
そこで今回は、どのようにして言語を身につけられるのか、という点に関して、ヒトの「母語獲得」を「外国語習得」に絡めながら説明し、さらにどのような取り組みが必要なのか考えていきます。
音素のカテゴリー構築
 すべてのヒトは、幼児期にはあらゆる音素を聞き分ける力を持っています。これは学問分野によって様々な呼び方がされますが、一般には Universal Phoneme Sensitivity(普遍的音素感受性)と呼ばれます。胎内で聴覚が発達すると、子どもは周囲の言語環境、つまり母語(“L1 : Language 1、第一言語”)の音声に晒されるようになります。しかし、この段階ではまだ特定の言語に最適化されておらず、世界のいかなる言語の音声にも高い感受性を持っています。
すべてのヒトは、幼児期にはあらゆる音素を聞き分ける力を持っています。これは学問分野によって様々な呼び方がされますが、一般には Universal Phoneme Sensitivity(普遍的音素感受性)と呼ばれます。胎内で聴覚が発達すると、子どもは周囲の言語環境、つまり母語(“L1 : Language 1、第一言語”)の音声に晒されるようになります。しかし、この段階ではまだ特定の言語に最適化されておらず、世界のいかなる言語の音声にも高い感受性を持っています。
胎児は、すでに胎内でも母親の声をローパスフィルター越しに聞いており、その音声は低周波成分が中心です。したがって、日本語の母音の細かな区別がどの程度できているかは微妙ですが、男女や子どもといった声質の違い、ピッチ(高低)、韻律(プロソディー)などの大まかな特徴は胎内で受け取っています。これは、ヒトは本来すべての音声を知覚する能力を持っているものの、その音声をどう処理するかという L1 音韻知識(phonological knowledge)が、胎内から徐々に形成され始めることを示しています。
そして、生後1歳頃を迎える頃には、聞いた音声は日本語の音韻カテゴリを通して処理されるようになります。これを Perceptual Narrowing(知覚の狭窄化)と呼びます。この知覚の狭窄化によって、母音空間の範疇化が始まり、ヒトの音声世界はその子が接している言語の音韻体系に向かってチューニングされていきます。
母音空間は、英和辞典などに見られるいわゆる台形図の形で示されます。日本語ではこの空間を「ア・イ・ウ・エ・オ」の5つに大きく分けますが、英語では12以上に細かく分けます。知覚の狭窄化によってこの「分け方」そのものが L1 に特化していくため、英語の hat, hot, hut /hæt – hɑt – hʌt/ は本来まったく異なる音なのに、日本語の L1 音韻論ではすべて「あ」に分類されてしまいます。
この L1 を通した音声の処理は、言語心理学では、母語プロセス(native language magnet effect などを含む L1-based perception)として知られています。日本語に /l/ と /r/ の対立がないため、英語の /l/・/r/ は同じカテゴリに吸収されます。英語の /f/・/v/ も、日本語では /ɸ/ や /b/ に同化して解釈されますし、/θ/・/ð/ は /s/・/t/・/z/・/d/ のいずれかに置き換えられます。いずれも「母語の枠組みで外国語を聞く」ことによる自然な現象です。
この現象を理論的に説明したものが “PAM : Perceptual Assimilation Model、知覚同化モデル” です。PAM によれば、“L2 : Language 2、第二言語” の音は、まず L1 のどの音に「同化」されるかによって、聞き取りの難しさが決定します。たとえば、日本人が /r–l/ を聞き分けにくいのは、英語の /r/ と /l/ が日本語の「ラ行」という、ひとつの L1 カテゴリに同化(Single Category)されてしまうためです。つまり「違う音」として処理される前に、「同じ音」に収納されてしまうのです。
一方、発音習得の観点からは、 “SLM : Speech Learning Model、音声学習モデル” が知られています。SLM では、L2 の音が L1 に“どれくらい似ているか”という距離が、発音習得の成否を左右すると考えます。L2 の音が L1 に似ているほど(たとえば /r/ と /l/ のように)、学習者はその音を新しいカテゴリとして保持しづらく、逆に L1 にない音は新規カテゴリを形成しやすいのです。このため、日本人が英語の子音や母音を聞き間違えたり発音しづらい理由は、PAM の「同化」と SLM の「距離」という 2 つの理論でよく説明できます。
以上の流れから分かるように、胎内から1歳頃にかけては日本語以外の言語に対する敏感性が十分に残っています。しかし、3歳頃には日本語(L1)の文法的な枠組みが形成され、7歳頃には平仮名・片仮名の正書法が確立し、小学校中学年から思春期にかけては音読能力も発達し、L1 音韻知識がほぼ完成に向かいます。このように段階的に英語(L2)の知覚や産出が苦手になり、最終的には思春期のいわゆる「臨界期(Critical Period)」からはガクンと学習能力が落ちます。
この一点を見ても、英語を含む外国語の学習は、日本語の音韻知識が固定化する前、できるだけ早い時期に始めた方が有利であることが理解できます。
しかし、別の角度から見れば、これは極めて自然なことです。L1 音韻論にチューニングされるということは、聞き取り能力が“失われる”ことではなく、母語の処理能力が極めて高くなるという意味でもあります。成長によって L1 への敏感性が高まり、聞き取ろうとしなくても隣の席の会話が理解できたり、騒音の中でも必要な音声だけを抽出できたりします。さらに驚くべきことに、L1 の音韻知識は、部分的に欠損した音声でさえ補完し、意味のある連続音として再構築してくれます。これは、母語を持つことの大きな恩恵であり、人間の認知の巧妙さを表しています。
このように、Universal Phoneme Sensitivity → Perceptual Narrowing → 母語プロセス → PAM → SLM という流れは、私たちがなぜ外国語を聞き取りにくいのか、そしてなぜ早期学習が有益なのかを分かりやすく説明してくれます。同時に、母語を獲得する人間の能力がいかに高度で、いかに恩恵の大きいメカニズムであるかを示しているのです。(参考『パルキッズ通信2025年3月号 英語のスタートは早いほど良いたった1つの理由』)
音節構造の理解
 前章では、幼児が生後1年頃にかけて日本語(L1)の音韻カテゴリーへ最適化され、英語(L2)を日本語の音として処理してしまうことを見てきました。ここからは、さらに上位の単位である、音節および形態素に話を進めます。語とは一般に「独立して発話できる最小単位」を指しますが、助詞や接続詞、接尾辞のように独立しては発話しないが意味や機能を担う単位も含め、これらを総称して形態素と呼びます。
前章では、幼児が生後1年頃にかけて日本語(L1)の音韻カテゴリーへ最適化され、英語(L2)を日本語の音として処理してしまうことを見てきました。ここからは、さらに上位の単位である、音節および形態素に話を進めます。語とは一般に「独立して発話できる最小単位」を指しますが、助詞や接続詞、接尾辞のように独立しては発話しないが意味や機能を担う単位も含め、これらを総称して形態素と呼びます。
語の最小性制約によれば、2音節・2モーラ(拍)の語がもっとも自然な形(無標)とされます。3モーラ以上の語が2モーラに縮約されたり、1モーラ語が2モーラに拡張されたりするのは、ヒトの言語処理がまず普遍的な形から入り、その後、言語固有の有標的(特殊)な形へ細分化していくためです。ここで重要なのは、人間にとって無標なのは英語に代表される音節構造であり、日本語のようなモーラ構造はむしろ言語類型的には有標であるという点です。実際、日本人の幼児は「ブランコ」「ベランダ」を /bu.ran.ko/、/be.ran.da/ のように三拍でとらえることが多く、最初は音節単位で世界を切り取っています。それが「かな文字」というモーラ単位の表記体系を学ぶ頃から、/bu.ra.N.ko/、/be.ra.N.da/ のようにモーラ分節へと再編成されます。
この L1 的な「区切り方」は、英語学習にも強く影響します。英語は閉音節を多く持ち、たとえば on a chair の on は子音で終わる閉音節です。しかし、日本語話者はモーラ的な CV 構造(子音+母音)に慣れているため、/on/ を「オ・ン」と二つに割って処理したり、母音を補って「オンナ」のように開音節へ変形したりすることがあります。結果として on a chair を「オンナチェア」→「女チェア」のように誤って捉えるのです。これは音素レベルの L1 同化(PAM/SLM で説明される現象)が、音節レベルでも生じている例といえます。
一方、語や形態素の習得には、無標性以外にも頻度・親密度・近傍密度・音素配列規則(フォノタクティクス)が影響します。英語では語の約6割が閉音節を含み、子音連続も /str-/ や /spr-/ のように出現頻度が高い一方、日本語はほぼ CV 構造で、コーダ(音節末子音)も限定的です。このため、日本語話者は英語の閉音節や子音連続を「頻度の低い構造」として処理し、不安定なため、日本語的モーラに切り直したり、母音を挿入して再構成したりします。
しかし、これは「英語が習得できない」ということではありません。音素の節で述べたように、SLM では L2 音が L1 カテゴリーの“範囲外”に十分な量出現すると、新たなカテゴリが形成されると説明します。同じことが音節・形態素レベルにも当てはまり、英語特有の閉音節、弱形の機能語、子音連続に継続的かつ大量に触れることで、学習者は日本語の枠では説明しきれない音節パターンを統計的に蓄積し、徐々に「英語的な区切り方」を身につけていきます。
つまり、L1 にチューニングされていることは不利ではなく、むしろその土台の上に、L2(英語)用の新たな音節・形態素カテゴリーを上乗せできるのです。重要なのは、継続的インプットによって、日本語的なモーラ分節から少しずつ離れ、英語本来の音節構造へ近づけていく学習環境を整えることだといえるでしょう。(参考『パルキッズ通信2024年11月号 言語獲得について現代の言語学でわかっていること』)
形態素や語の発見から辞書への登録
 インプットによって、音素のカテゴリーが構築され、英語の音節の体系も学習されます。これだけでも驚異的なことです。一般的な日本人は、英語の音素のカテゴリーも頭の中になければ、音節構造や、それが生み出す様々な音韻処理もできません。上で述べたように、英語では音節末子音が後続する母音に吸着される子音誘引、あるいは再音節化といった音韻過程が存在します。
インプットによって、音素のカテゴリーが構築され、英語の音節の体系も学習されます。これだけでも驚異的なことです。一般的な日本人は、英語の音素のカテゴリーも頭の中になければ、音節構造や、それが生み出す様々な音韻処理もできません。上で述べたように、英語では音節末子音が後続する母音に吸着される子音誘引、あるいは再音節化といった音韻過程が存在します。
例えば、母音に挟まれた ’t’(butter, water, a lot of)はフラップ音に変化します。これは、先行する音節(but., wat., a lot., )のコーダ(音節末子音の)子音が後続する母音に引き寄せられることから、両音節性(ambisyllabicity)となるときに ‘t’ が日本語の「ラ行」の音に変化するのです。このような音韻処理は、英語の音素と音節の知識が、言語回路として頭に存在しないことには、自然に為されることはありません。
さて、音素という部品が音節を作り、音節という部品は語や形態素、あるいはフレーズを無限に生み出します。それらの部品の目録が頭の中にできあがると、今度は聞き取った音節から作られた語を知覚できるようになります。
学校英語での語の知覚はトップダウンで行われますが、インプットから育った語の知覚能力はトップダウンでなくボトムアップです。トップダウンとは、心内辞書にインデックスされた語を、連続音声の中から探しに行く語の知覚方法です。この場合、知らない語は発見できないので、無論聞き取れません。また、子音吸引したり、母音間フラップが起きたりすると、これらも聞き取ることができません。なぜなら、心内辞書に登録されている音韻情報とは音節構造が変わってしまっているからです。
日本人の多くは、このようにしてトップダウンで英語を聞き取ろうとします。すると知っている語だけ、あるいは音韻構造が変化していない、生の状態で句に組み込まれている語のみを知覚できることになります。つまり、歯抜け状態です。そして、歯抜け状態の語の集合から、句の意味を想像する、というなんとも心もとない英語のリスニングをすることになるわけです。
他方、インプットで学ぶパルキッズたちのボトムアップ処理はまったく様子が異なります。日本語を耳にする場合を想像してください。耳を傾けて聞き取ろうとしなくても、日本語の文は自然と語の連続として聞こえてきます。つまり、文節までは自動的に脳が行ってくれているのです。これを英語でもやってしまうのが、パルキッズたちです。
さて、そのようにして聞き取った語は、次に心内辞書にインデックス登録されます。我々が30年ほど前から提唱している語句を用いれば「仮語彙」という状態です。辞書には通常、見出し語、発音、品詞、語源、そして意味内容と例文が登録されています。仮語彙の状態というのは「見出し語」の音韻情報のみ登録されている状態で、綴りすらも登録されていません。パルキッズたちは、聞き取った語を次々とインデックスに登録していきます。つまり、「聞いたことがあるが意味はわからない」状態です。
日本人は、学校の英語教育に慣れすぎていて、幼児英語におけるインプットを考えるときに、すぐに「意味はどうする?」と考えてしまいます。しかし、見出し語のみを仮語彙として登録するやり方は、我々を含め日本人が日本語を身につけていく段階でも日常的に行っていた作業です。それを単に英語に置き換えて習得させようというのが「パルキッズ」の考え方です。
心内辞書の充実
 このようにして、聞き取った語がまず「見出し語」の音韻情報として仮語彙に登録されると、次に必要なのは、異なる文脈での繰り返しのインプットです。語は1回聞いただけでは意味をもたず、辞書的な定義にも到達しません。しかし、別々の場面・異なる文脈・異なるイントネーションや速度で同じ語が繰り返し現れることで、音韻情報に加えて、意味・使用場面・結びつく語(コロケーション)が徐々に蓄積されていきます。
このようにして、聞き取った語がまず「見出し語」の音韻情報として仮語彙に登録されると、次に必要なのは、異なる文脈での繰り返しのインプットです。語は1回聞いただけでは意味をもたず、辞書的な定義にも到達しません。しかし、別々の場面・異なる文脈・異なるイントネーションや速度で同じ語が繰り返し現れることで、音韻情報に加えて、意味・使用場面・結びつく語(コロケーション)が徐々に蓄積されていきます。
この蓄積の仕組みを説明する理論が、認知言語学などで知られるイグザンプラーモデル(Exemplar Model)です。もうひとつ、プロトタイプモデルという考え方があります。前後しますが、プロトタイプモデルでは、対象の見出し(音声であったり文字であったり)と意味(イメージであったり定義であったり)をペアで登録していきます。幼児教育に使用される「フラッシュカード」はこの位置づけです。
他方のイグザンプラーモデルでは、語彙はひとつの抽象的な「意味=定義」を覚えるのではなく、実際に遭遇した使用例(exemplar)を多数ストックしていくことで形成されると考えます。つまり、辞書のように“意味をひとつ暗記する”のではなく、実際の言語使用のデータベースが脳内に構築され、その統計的中心(プロトタイプ)が「その語らしさ」として形成されるのです。辞書には、意味とその意味として使われている例文が提示されていますが、その例文がストックされていると考えればよいでしょう。
日本語を思い出してください。私たちは幼少期に「辞書を引いて語彙を増やした」わけではありません。親の言葉や周囲の会話、アニメ、絵本、幼稚園の先生などから入ってくる膨大なボトムアップの音声インプットによって、語を文脈の中で何度も経験し、気づけばその語を「知っている」状態になっていました。語の意味を辞書的に説明できなくても、適切な場面で使うことができる―これが幼児の語彙獲得の本質です。
同じことが英語にも当てはまります。仮語彙として登録された語は、その後、さまざまな文脈で聞くことで、
・音韻的な揺れ(弱形、連結、フラップ化など)
・文脈的手がかり(状況、登場人物、意図)
・共起関係(よく一緒に出てくる語)
・プロソディー(強弱、リズム、イントネーション)
といった要素が積み重なり、語の「内的辞書」が豊かになっていきます。
この“辞書のページを自動的に増やしていく作業”は、日本語(L1)では誰でも自然に行っています。英語(L2)でも同じで、カードを見せなくても、辞書を引かなくても、十分なバラエティと繰り返しをもつインプットが与えられれば、語彙は自然と豊かになっていきます。むしろ、辞書的定義を先に覚える学習(トップダウン)は、母語話者の語彙形成とは異なるプロセスであり、子どもにとっては非自然的です。
つまり、語は「教えられるもの」ではなく「経験されるもの」です。音韻カテゴリーの構築 → 音節の知識化 → 語の抽出 → 仮語彙登録 → 文脈インプットの蓄積という階層的プロセスを経て、語彙は少しずつ意味と使用を獲得していきます。私たち日本人が日本語で行ってきたことを、そのまま英語にも適用するだけで、辞書を引かずとも豊かな語彙が育つのです。
シンタクスへ
 文脈インプットによって語が仮語彙から「使える語」へと育っていくと、今度はそれらの語が組み合わされて文として理解される段階に入ります。語が単独で意味を持つようになるだけでは、言語理解は完成しません。語と語の組み合わせ、語順、プロソディー、そして文脈が統合されて、初めて「意味のある文」として理解されます。
文脈インプットによって語が仮語彙から「使える語」へと育っていくと、今度はそれらの語が組み合わされて文として理解される段階に入ります。語が単独で意味を持つようになるだけでは、言語理解は完成しません。語と語の組み合わせ、語順、プロソディー、そして文脈が統合されて、初めて「意味のある文」として理解されます。
このとき脳内で起きているのが、認知言語学でいう「命題的表象(propositional representation)」や「状況モデル(situation model)」の形成です。ひと口に言えば「心内表象」の作業で聞き取った語が、それぞれの意味と文脈的な手がかりを伴って脳内で統合され、「何が起こっているのか」「誰が何をしたのか」等の内容が映像として再構築されていきます。幼児の言語理解が急激に進む理由は、この状況モデルが爆発的に機能し始めるからです。
余談ですが、「大河を横切るハイウェイは左手へ長く緩やかな登り勾配の弧を描きながら雪国へと入っていく」という文を読めば、十人十色に「状況モデル」が構築されます。状況モデルはこのようにイメージに直結している一方、命題的表象は「物語文は語彙を豊かにするが、説明文がそうであるような理解力の涵養には直接結びつかない」という文から分かるように、命題を構造化するような理解です。
ところで、英語の教材を見てください。幼児向けのものから学生向けのものまで、ほとんどが「物語文 → 状況モデル」からの理解を促すように作られています。つまり、文体が物語文に偏っており、説明文が少ないのです。これはイメージ的な理解を促す物語文、あるいは卑近な説明文のほうが初歩の言語学習に適していることから、その様になっているのでしょう。
このように、イメージしやすい物語文や直感的な説明文から構成されることで理解が容易に為されるのは、ほとんどの L2 英語教材に共通する点でしょう。また、挿絵があることも一般的ですので、さらに文脈理解は容易になります。閑話休題。
さて、このような教材を用いた学習では、語の細部があいまいであっても、文脈から全体を把握するのは容易です。たとえば、come と came のように、音韻的に似ている語や弱形化して聞こえにくい語であっても、文脈によって時制や意味が補完されることが多くあります。「昨日の話」なら過去形、「いま起きている出来事」なら現在形と判断するわけです。これは母語で行っている処理とまったく同じ仕組みであり、英語でも十分に可能です。
つまり、音素 → 音節 → 語 → 仮語彙 → 文脈経験という階層を経て育った語彙は、最終的に文としての理解へ自然につながっていきます。文法(grammar)とは本来、「文を構成する自然な規則性」を、脳が自動的に抽出した結果であり、必ずしも明示的に教えられる必要はありません。実際、日本語(L1)の文法を幼児が学んだときも、そのような説明は一切受けていませんでしたが、彼らは(我々も含め)自然なインプットから時制・相・法制などは身につけることができたのです。
あとは読むだけ ── カテゴリーは読みの経験で頑強になる
 音声インプットによって音素・音節・語・文のカテゴリーが構築されると、最後に必要なのは「読みの経験」(literacy)です。読みとは、耳から得た言語の構造を「視覚情報」として再度入力する作業であり、これによって言語カテゴリーは一層強固になります。
音声インプットによって音素・音節・語・文のカテゴリーが構築されると、最後に必要なのは「読みの経験」(literacy)です。読みとは、耳から得た言語の構造を「視覚情報」として再度入力する作業であり、これによって言語カテゴリーは一層強固になります。
音声だけで習得した語彙や文法は、柔軟で運用にも優れていますが、さらに、視覚的な文字体系と結びつけることでカテゴリーが安定し、精密化されるというメリットがあります。音声で形成された語彙が、スペリング・文字列・句読点・文構造と結びつくことで、語彙の意味領域が広がり、あいまいさが解消され、表現も豊かになります。
これは日本語でも同じでした。幼児期に音声だけで習得した語彙は、ひらがな・カタカナ・漢字を学ぶことで意味の細分化が可能になり、語と語の関係性(類義語・対義語・上位語・下位語)が視覚的にも認識できるようになります。英語でも、音声で得たカテゴリーが読みと書きの経験を通してさらに頑強化され、抽象的な思考や学術的な理解へと進化していくのです。
すでに音声インプットによって大量の語を聞き取り、語彙の仮登録も済んでいる「パルキッズ」育ちの子どもたちは、読み始めると一気に語彙が結晶化していきます。音で知っていた語が文字として認識され、既存の音韻カテゴリーと結びついて、語彙体系が飛躍的に拡大するのです。
◆ まとめ:音 → 音節 → 語 → 文 → 読みへ
このように、
1. 音素カテゴリーの構築(PAM/SLM)
2. 音節・音素配列規則の学習
3. 語・形態素・フレーズの認識(ボトムアップ)
4. 文脈インプットによる語彙の意味獲得(イグザンプラーモデル)
5. 文理解(状況モデルによる心内表象)
6. 読みでの頑強化
という順序で言語能力は積み上がり、互いに補強し合いながら発達していきます。
音声インプットを十分に受け、文脈を通して語を経験し、最終的に読み書きと接続する——「パルキッズ」で具現化する、この自然な流れこそが、母語と同じプロセスで英語を身につけるための王道なのです。
【編集後記】
今回の記事をご覧になった方におすすめの記事をご紹介いたします。ぜひ下記の記事も併せてご覧ください。
★「忙しい」X「頑張らなくて良い」=「おうち英語」
★「インプット」で育てる「国語力」が学力すべての土台となります
★完・船津流「育児論」
★認知力?非認知力? 大切なのは…
★ことばを伸ばす親の話し方
【注目書籍】『地頭力を鍛える子育て』(大和出版)
 子どもが「読めるのに、わからない」状態を家庭から終わらせる——。
子どもが「読めるのに、わからない」状態を家庭から終わらせる——。
言語学者・船津洋が提唱する“地頭力”とは、認知×非認知×メタ認知の三位一体の力。本書では、日常の会話や体験を通じて「理解・思考・判断」を育む具体的な方法を提示。学力だけでなく、生きる力を伸ばす実践書です。


船津 洋(Funatsu Hiroshi)
株式会社児童英語研究所 代表、言語学者。上智大学言語科学研究科言語学専攻修士。幼児英語教材「パルキッズ」をはじめ多数の教材制作・開発を行う。これまでの教務指導件数は6万件を越える。卒業生は難関校に多数合格、中学生で英検1級に合格するなど高い成果を上げている。大人向け英語学習本としてベストセラーとなった『たった80単語!読むだけで英語脳になる本』(三笠書房)など著書多数。