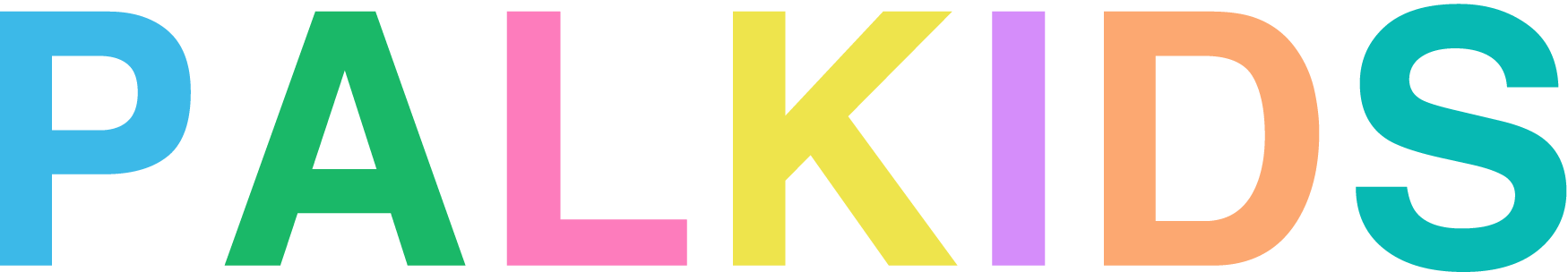パルキッズ通信 特集 | 大量インプット, 学校英語教育, 英語学習方法, 言語学, 言語獲得
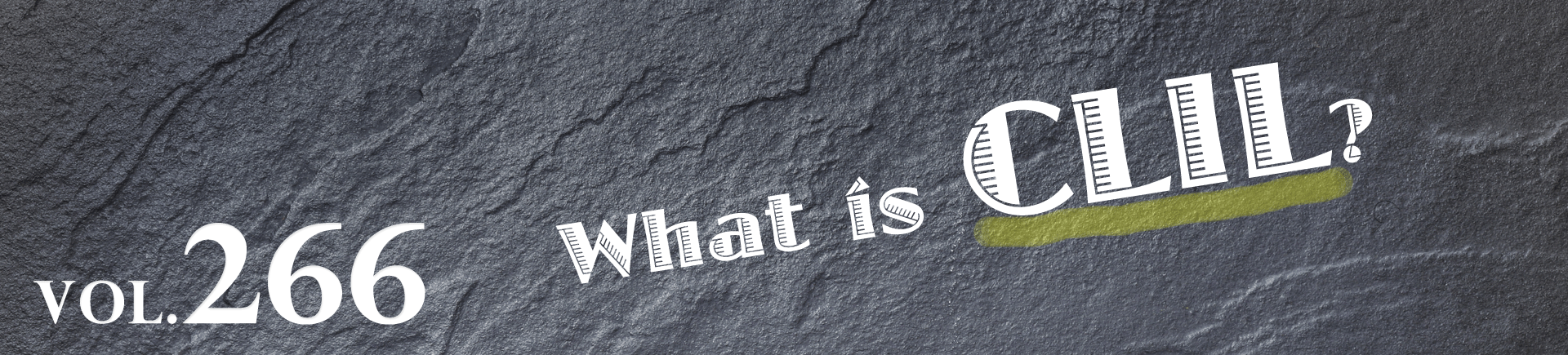
2020年5月号特集
Vol.266 | “CLIL” って何? 効果あるの?
なんちゃってCLILとホンモノのCLILと見分けるために知っておきたいこと
written by 船津 洋(Hiroshi Funatsu)

船津 洋(Funatsu Hiroshi)
株式会社児童英語研究所 代表、言語学者。上智大学言語科学研究科言語学専攻修士。幼児英語教材「パルキッズ」をはじめ多数の教材制作・開発を行う。これまでの教務指導件数は6万件を越える。卒業生は難関校に多数合格、中学生で英検1級に合格するなど高い成果を上げている。大人向け英語学習本としてベストセラーとなった『たった80単語!読むだけで英語脳になる本』(三笠書房)など著書多数。
 最近しばしばお目にかかる “CLIL : Content and Language Integrated Learning、内容言語統合型学習、クリル”。新しい物好き、お題目好きの我が国民性にピタリと合って(いるかどうかは知りませんが)、公教育にも民間にも広がりを見せています。今回はそんな “CLIL” の本質に迫る話です。
最近しばしばお目にかかる “CLIL : Content and Language Integrated Learning、内容言語統合型学習、クリル”。新しい物好き、お題目好きの我が国民性にピタリと合って(いるかどうかは知りませんが)、公教育にも民間にも広がりを見せています。今回はそんな “CLIL” の本質に迫る話です。
まず、今回の話のロードマップを示しておきます。
テーマは「モチベーションとCLILの関係」です。何かをするには、まず①モチベーションがあり、成果を得るために②優れた方法の選択が必要です。
前後しますが、最初に②の選択肢のひとつとして提示されているCLILが、どのようにして生まれたのか、その背景に迫ります。さらに①のモチベーションの話を織り交ぜながら、日本におけるCLILを眺めて行きたいと思います。
もちろん、エッセイですので毎度のごとく気ままに脱線しながら書き進めて参りたいと思います。最後までお付き合いいただければ幸いです。
その前に、ひとつ注意です。ひょっとすると、読者の皆様は読み進めるうちに、私が「CLIL批判」を展開しているだけではないのか、と訝る方もいらっしゃるかも知れません。しかし私自身、CLILで英語を身につけた人間の一人ですし、CLILは至極真っ当な考え方だと判断しています。ただ、その運用方法に問題があると考えていることを、予めお伝えしておくことにいたします。
それでは、始めましょう。
CLILって何?
 CLILとは、1994年にDavid Marsh により提唱された言語教育の方法論のことで、従来の外国語教育のようにフォーム(形式:規範文法等の規則)ではなくコンテンツ(意味内容:数学や歴史など対象)の学習指導に主眼を置かれるのが特徴です。
CLILとは、1994年にDavid Marsh により提唱された言語教育の方法論のことで、従来の外国語教育のようにフォーム(形式:規範文法等の規則)ではなくコンテンツ(意味内容:数学や歴史など対象)の学習指導に主眼を置かれるのが特徴です。
ご本人の言を引用すると「(CLILとは)主に第一外国語など母語以外の言語を媒体として言語以外の教科を教授・学習させる “dual focus(二重焦点)” のあらゆる手段」だそうです。
なにやら分かったような分からないような記述ですが、それもそのはず、どうやら従来の学校英語のようにフォームを教えるのではなく、コンテンツに焦点が当たっていれば、それはすべてCLILのようなのです。
CLILの始まりは海外です。
昔から日本人にとっては、外国語習得の必要など、これっぽっちもありませんでした。日本は海に囲まれていて縦に長いので、豊富な海洋資源と農作物に恵まれています。人もそこそこ多いので鎖国してもどうにかなりました。これは、少なからずの日本人の意識の中では、今日に至っても事実です。
ところが、一歩日本を出ると状況は異なります。大陸では物理的に言語の異なる地域と隣接していたり、また移民など人の流動が激しかったりと、外国語を使ったコミュニケーション能力への欲求は、日本とは比較にならないほどの重みを持っています。
そんな中、80年代から90年代にかけてさまざまな外国語習得法が提唱されてきました。CALLA, CBI, CBLI, EMI, FLIP, LAC, LBCT, TFL, WAC などなど、例示すれば限りがありません。
まぁ、ひと口に言えば、文法教育に見切りをつけた教育者や政治家を中心とした人たちが、思い思いの方法を編み出してきた。そして、それらすべてをひっくるめて「ガラガラポン」と出てきたのがCLILということのようです。
以下、もう少し詳しく見て参ります。
そもそも外国語なんて不要?
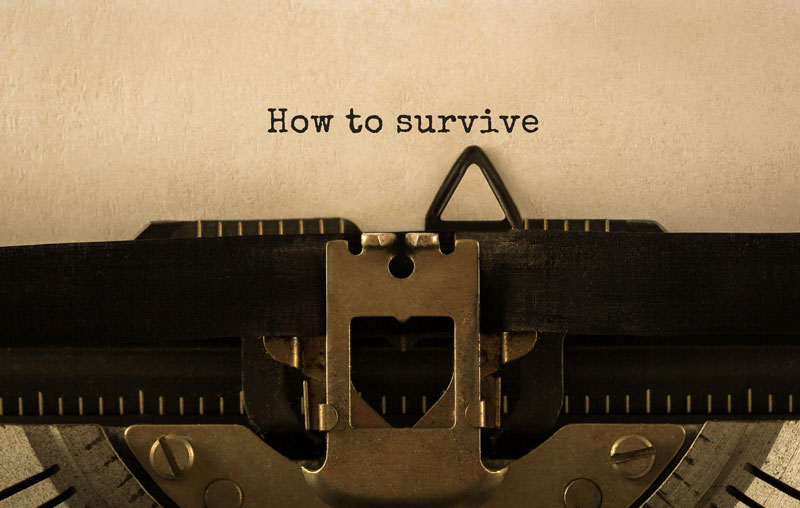 外国語教育に関するモチベーションについて、CLILに至るまでの歴史を併せて考えてみることにします。
外国語教育に関するモチベーションについて、CLILに至るまでの歴史を併せて考えてみることにします。
外国語教育は古代から行われていますが、そもそも人々はなぜ外国語を必要とするのでしょうか。これに答えられなければ、お子さんの英語教育、あるいは日本で行われている英語教育の目的がクッキリしませんね。また、なぜCLILが生まれたのかも分かりません。
さて、なぜ外国語教育を必要とする人たちがいるのでしょうか。
これには様々な理由が挙げられるでしょう。しかし、人類の歴史をひもとけば、外国語習得の主な目的は、つまるところ「生き残り戦略」です(←ココ重要ですので覚えておいてください)。言葉が異なる人たちとコミュニケーションが成立しなければ、商圏も広がりませんし、諍いも絶えないでしょう。それを解決するのが、外国語を含めた言語能力なのです。「話せば分かる」わけです。
言い換えれば、外国語ができれば人脈や市場が広がるので、商売や政治にとっては好都合です。島国の人たちのように、ご近所さんたちばかりと引きこもっていれば、外の世界の潮流から取り残されてしまいます。(もっとも、そのおかげで世界的にも未曾有の文化を生み出すこともありますが、結局は政治と経済で他に追いつくため、後に大変な苦労をするわけですし、現に日本は明治期にそれを経験しました。)
つまり、外国語は経済的にも政治的にも、身の安全を保つためには極めて強力なツールなのです。これは、国家においても然り、個人においても然りです。そのツールの獲得が、言語習得への強力なモチベーションです。
すると、何が起こるか。
古来から主に金銭的に余裕のある層は、子女に外国語教育を施してきました。選択されていた方法は主に2つ。ひとつはターゲットの言語が話される国へ子どもを放り込んでしまうこと、もうひとつは家庭内で専任の外国人チューターを雇い、ターゲットとなる言語で自然科学を始めとした学問を仕込む方法です。
これだけでも、外国語習得はお金持ちに限られていた特殊な教育であることが分かります。まさに二極化ですね。
その後、少し時代が下ると grammer school のような、子息をラテン語で教育する学校もできました。そこでは、実際にラテン語で作文させられたりしていたようです。
留学にしても、チューターにしても、グラマースクールにしても、子どもたちは実際に外国語の使用を強制される、いわゆるイマージョンの環境で外国語を身につけさせられたわけです。(『History of CLIL Hanesova』)
そしてヨーロッパでは
 さて、その後、外国語教育は学校制度が充実するにつれて、お金持ちだけのためのものではなく、広く一般大衆にも施されるようになります。しかし、古今東西言うまでもありませんが、これがなかなか成果が上がらないわけです。
さて、その後、外国語教育は学校制度が充実するにつれて、お金持ちだけのためのものではなく、広く一般大衆にも施されるようになります。しかし、古今東西言うまでもありませんが、これがなかなか成果が上がらないわけです。
他方、外国語習得のニーズはどんどん高まっていきます。特にヨーロッパでは60年代になると、従前のヨーロッパ経済共同体などを統合したECが誕生します。もちろん経済的な理由です。バラバラでいるよりは、まとまった方が大きな力になりますからね。
もちろん、そのためには言葉が通じることが大前提です。そこで、外国語教育のニーズも必然的に高まっていくわけです。
そして、そのような経済的なニーズを政治が後押しします。70年代になると欧州委員会により「2カ国語以上による学校教育」が推奨され、80年代には欧州議会が「外国語教育の改善に踏み出す」ことを打ち出します。多くの学校で複数の “教科を外国語で” 教えることが広がっていきます。
さらっと書きましたけれども、外国語を教えるのではなく、 “教科を外国語で” 教えるというところがミソです。
背景を察するに「変わら(れ)ない外国語教育」にしびれを切らしたお上や専門家が「外国語教育」そのものには手をつけずに、古人に習った「イマージョン」を参考に「じゃあ、教科のいくつかを外国語で教えたら良いんじゃない?」となったのでしょう。
この考え方は、後のEUの「多言語主義」、「多様性の中の統合」という考え方に引き継がれ、すべてのEU市民が少なくとも2つ以上の言語を操れるようにすることが目指されるようになりました。
重要なポイントは、言語科目ではなく言語以外のコンテンツ(この場合は教科)を、母語以外の言語で教える、という点です。ここでは、フォーム(文法など)の指導は最小限に抑えられます。
八方美人のCLILさん誕生
 さて、このような経済的・政治的・地理的な理由が「モチベーション」となって「外国語習得」が熱くなる。しかし、一向に成果の上がらない外国語教育がある。そこで、すでに述べたように「コンテンツ」経由の数多くの外国語教授・習得法が、90年代にかけて雨後の竹の子のように生まれてきたわけです。
さて、このような経済的・政治的・地理的な理由が「モチベーション」となって「外国語習得」が熱くなる。しかし、一向に成果の上がらない外国語教育がある。そこで、すでに述べたように「コンテンツ」経由の数多くの外国語教授・習得法が、90年代にかけて雨後の竹の子のように生まれてきたわけです。
そして、それらを総合する “umbrella term(総称)” としてのCLILの誕生と相成ります。
しかし、うまいこと考えたものです。CLILのすごいところは、どこからも文句が出ないところです。あらゆる外国語学習法と親和性が高いのです。以下の具合です。
”dual focus(二重焦点)” と銘打つことで、外国語以外の教科の先生も「外国語教育」に参加することになりますが、これは「外国語教師の聖域」を侵すものではありません。あくまでも「教科の教育」つまり別枠です。
また、”dual focus” の名の下、文法・訳読の教授法の能力のみではなく、経験的外国語(実際の運用)能力を発揮できる外国語教諭は、大手を振って外国語による外国語の授業を運営することができるようになるわけです。
一人取り残されるのは、従来の分析型外国語教育(文法・訳読)しかできない教師たちですが、彼らにも自分たちのテリトリーはあるわけですから、それはそれで結構なことなのです。
このような性格から、CLILは急速に広がりを見せます。 “4C” とか “dual focus” の名の下、皆こぞってCLILを実践し始めるわけです。名ばかりのCLILすら少なくないようです。だって、便利なんですもの。”CLIL” と言えば、みんな「うんうん」となるわけですからね。まるで人を黙らせる魔法の呪文です。
もちろん、それでうまく行くかどうかは別次元の話です。
ヨーロッパでの成果
 そう。それが問題です。果たしてその効果の程は?となると、ズバッと明確に答えられる人はどれほどいるのでしょうか。
そう。それが問題です。果たしてその効果の程は?となると、ズバッと明確に答えられる人はどれほどいるのでしょうか。
ヨーロッパでのイマージョン式外国語教育、つまり外国語を教えるのではなく外国語でコンテンツを学ぶ方式は、カナダ・ケベック州での成功例を模範にした一面があるようです。しかし、ケベックでうまくいったことが、ヨーロッパでうまくいったとは言い切れませんでした。
カナダの中でも、ケベックはフランス語話者が多い特殊な環境にあります。
カナダ全体を見るとフランス語話者が2割ほどで、英仏のバイリンガルも2割ほどです。つまり、数字だけでみれば、英仏バイリンガル(英語が母語)ではなく仏英バイリンガル(仏語が母語)が圧倒的に多いことになるでしょう。そして、それが集まっているのがケベックです。
言ってしまえば、「カナダでの成功例」は、教育がある程度充実した先進国の中での、しかもフランス語と英語という枠組みの中での限定的な成功なのです。(『Fast figures on Canada’s official languages』)
その英語とフランス語ですが、これらの言語は歴史的に深いつながりがあります。コーパス分析(←説明はしません)の方法によりますが、英語における、フランス語やラテン語などロマンス語からの借入語が6割、イタリック語派まで広げれば7割以上になるでしょう。つまり、英語とフランス語とは「血の繋がった家族」とは行かないまでも「夫婦」のような、ラテン語とは「孫と祖父母」みたいな関係なんです。
CLILの生みの親のMarshさんもご自身で仰られているように、「イマージョンは少数言語話者よりも多数言語話者には効果的」としています。つまり、ケベックの例は英語や仏語話者には有効でしたが、少数民族言語使用者には有効ではなかったようです。
しかも、繰り返しますが、実際は仏語話者による仏英バイリンガルがほとんどです。一方的に仏語話者が仏英バイリンガルになっている。これは言い換えれば、リンガフランカとしての地位が確立している英語だからこそ、仏語話者による英語習得へのモチベーションも高かったのではないでしょうか。
また、ヨーロッパのケースでも、スロバキアなどの国で、様々な理由であまりうまく行かなかったようです。当てずっぽうですが、少数言語使用者と同様に「母語とターゲット言語間の距離の問題」があるのではと考えてしまいます。
先述のフランスは特例(なにしろイギリスはフランス人が作った国ですから)としても、ドイツにしても英語の家族ですから、それらの国々でCLILが一定の成果を収めるのは、至極当然のことでしょう。(EUでよく使われているスラブ語系の言語については、まったくと言って良いほど知識が無いので、ここでは触れさせずにおいてください。)
当たり前のことですが、仮にある場所でうまくいっても、それが別の場所でうまくいくとは限りません。
①経済的・地理的・政治的条件も違えば、モチベーションも異なります。
②また、日本における英語を考えると、母語とターゲットの距離も大きく成否を左右する
と考えるのが健全な思考ではないでしょうか。
これもどこかで書いた「n=1」の例とも通じますが、とある成功例の一面のみを取り上げて、その表面を真似てもうまく行かないことが多いことは、すでに皆さんご存じのはずだと思います。それとも、募る思いのあまりそんな摂理は無視して論理飛躍すら見えなくなってしまっているのでしょうか。
「CLILを熱心に取り入れたいくつかの国々は、ついには “桃源郷” だと思っていたCLILが実は “幻想” だったことに気づくこととなった」などと、痛烈な表現をするCLIL専門家もいるほどです。しかも、その先生によれば「”what is CLIL?” という質問は、20年経った今でも妥当な質問だ」そうです。一体、CLILとは何なのでしょうか?(『The development of CLIL over the years』)
what is CLIL?
 そうなのです。どうやら外国語習得の必要に迫られた人々や、様々な理由でそれを後押しする国々の要求に現場が応える形でCLILが生まれ、広がっていったことは分かりました。また、CLILも万能ではなく、効き目のある人と、あまり効き目のない人がいることもわかりました。
そうなのです。どうやら外国語習得の必要に迫られた人々や、様々な理由でそれを後押しする国々の要求に現場が応える形でCLILが生まれ、広がっていったことは分かりました。また、CLILも万能ではなく、効き目のある人と、あまり効き目のない人がいることもわかりました。
では、我が国日本において、CLILはどのような当てはまり方をするのでしょうか。歯車のようにピタッとかみ合うのでしょうか。それには、やはりモチベーションとメソドを検証する必要がありそうです。
CLILという、なんだかよく分からないけど、有り難そうな言葉は最近になって一般的に耳にするようになりましたが、これは、どうやら上智大学の英語科あたりが旗振り役のようです。上智と言えば英語ですし文科省とも大の仲良し(?)です。そういえば、棚上げとなった外部試験の導入などの大学入試改革を始めとした「英語教育のあり方に関する有識者会議」の座長も上智大学の高名な先生でしたね。(『YouTube・英語教育改革の行方』)
ここはやはり彼ら、専門家の皆様の考え方に当たってみるのが、日本におけるCLILの本当のところの解明の糸口になるかも知れません。
日本のCLIL
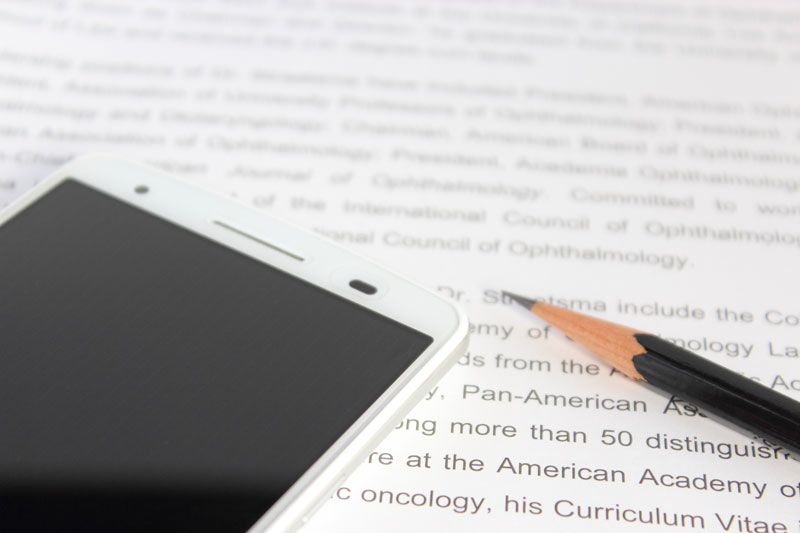 ということで、書籍や論文などにいくつか当たってみました。
ということで、書籍や論文などにいくつか当たってみました。
結論からいえば、日本におけるCLIL導入の考え方の根底には、以下の図式があるようです。
①英語ができる学生は間違いを恐れず英語で発信する傾向がある。
②英語ができない学生は文法学習に拘泥しており、発信を避ける。
∴(ゆえに)文法学習ばかりでなく、積極的に英語で発信することで英語ができるようになる。
単純化しすぎているので、専門家の諸先生方にはおしかりを受けるか知れませんが、彼らの主張を読んでいて様々なところに見え隠れする「失敗を恐れずに英語を使ってみたら英語はできるようになる」という信念(?)のようなものもは、上のロジックに通じていると感じられます。
しかし、違和感がなくもありません。もちろん、ヨーロッパでもすでに「外国語教育」の一環としてCLILは取り入れられていますが、基本は “教科を外国語で” 教えるのがCLILの始まりのはずです。これまたすでに述べたように、便利な言葉という性格から、CLILは随分恣意的に解釈・運用されているようです。
もっとも、これは厳しすぎる指摘かも知れません。日本でCLILを取り入れる場合には、まさか数学や社会科の教師が英語でそれらの教科を教える、などということは想像だにできないでしょう。従って、英語の教師がヨーロッパの一部の国でも行われているように「外国語教育」の枠の中でいわゆる “weak CLIL” を採用するのは致し方がないことでしょう。
この1点だけ取ってみても、カナダやヨーロッパの国々におけるCLILと、日本におけるCLILは、いかにかけ離れたものであるのかが分かると思います。
英語の出来る学生にも聞いてみた
 学生に、英語学習に対するモチベーションや、採用するメソドを直接調査することも行われています。以下は、同論文における「(平均以上に)英語はできる(といわれる)」上智大学生を対象に行われた調査です。(『Beliefs about Language Learning, Learning Strategy Use, and Self-Efficacy/Confidence of EFL Learners with and without Living-Abroad Experience』)
学生に、英語学習に対するモチベーションや、採用するメソドを直接調査することも行われています。以下は、同論文における「(平均以上に)英語はできる(といわれる)」上智大学生を対象に行われた調査です。(『Beliefs about Language Learning, Learning Strategy Use, and Self-Efficacy/Confidence of EFL Learners with and without Living-Abroad Experience』)
日本人学生が対象なのですが、海外経験者(6ヶ月以上)を多く含み、さらに主に2年生以上も含まれている点から、少なくとも海外で、あるいは学内でイマージョン式の学習を通して、ある程度以上に英語を身につけた学生たちが、英語に対してどう考えているのかも伺えるアンケートとなっています。
そのアンケート結果を他の研究と照らし合わせ、学生の英語力と英語使用のあり方を縦横に眺めてみると以下のようなチャートが出来上がります。
1、学習方法には分析型学習(文法・訳読)と体験型学習(言語の使用)があるが、いずれかの選択は指導者のそれに似る。つまり小学校英語は別としても、中学までに英語を身につけていなければ、子どもたちは学校の先生と同調して、体験型学習よりも分析型学習を好むようになる。
2、運良く留学を含めある程度以上(研究では6ヶ月としていますが、おそらく1年前後が中心)のイマージョンの経験があった場合、その子たちは他に選択肢がないので、体験型学習を余儀なくされる。結果として文法知識や和訳を経ずに英語を理解できるようになる。
3、他方、留学などのチャンスがないままの子たちは「話すこと」をしないばかりでなく「読むこと」もしない傾向にある。加えて英語でドラマを見たりメールを書くなどの英語自体との接触にも積極的ではないく、ひたすら「文法・訳読」の世界に逃げ込むようである。
(↑これは怖いですね。親も先生ですから、親が文法にこだわると、子どもも「成果の上がらない」といわれる文法学習に拘泥することになります。くれぐれもご注意ください。)
どうやら、留学のようにある程度強制的に追い込まれないと、分析型学習の軛を逃れることは叶わないようです。もちろん、純ジャパ(海外経験無しに優れた英語力を有する学生)も希に存在することは付け加えておきますが、彼らが「希」な存在であることも同時に強調しておきますし、彼らも知らず知らずのうちに体験型学習で英語に身を浸してきたことは間違いありません。
逆もまた然り?そんなわけはないでしょう
 繰り返しますが、CLIL推進派には「文法を気にせず英語を使ってみようよ」という気分があり、そこには、「英語ができる者は体験型の英語学習を好み」「英語のできない海外未経験者は、分析型学習に固執する」「ゆえに、分析型学習ばかりに拘泥せずに、体験型学習を取り入れれば英語はできるようになるよ!!」というロジックが根底に流れています。
繰り返しますが、CLIL推進派には「文法を気にせず英語を使ってみようよ」という気分があり、そこには、「英語ができる者は体験型の英語学習を好み」「英語のできない海外未経験者は、分析型学習に固執する」「ゆえに、分析型学習ばかりに拘泥せずに、体験型学習を取り入れれば英語はできるようになるよ!!」というロジックが根底に流れています。
なるほど、専門家の皆さんにこんなことを言われれば、政治家たちも英語が苦手な官僚も、文法ばかりじゃダメなんだなぁ、積極的に話すと英語力が身につくのか、と感じるのでしょうし、民間もそう信じざるを得ません。それどころか民間も、喜んでこの概念に飛びついています。本当にCLILって便利。
ついでながら、私自身も洋行帰りなので文法学習ばかりでなく、積極的な英語の使用を学習法としては強く信じる者であることは付け加えておきます。
しかし、上記のロジックには重大な瑕疵があります。「文法ばかり勉強しているから英語が身につかない。英語を身につけたければ英語で喋ろう」と、果たしてそれで英語ができるようになるのでしょうか。
無口だけど、実際に英語が出来る人たち
 以下は、実際に経験して感じたことです。
以下は、実際に経験して感じたことです。
上智の学生、特に英語科には帰国子女や留学生が多いのです。私も老人ながらその一人です。授業での学生たちの発言の様子を見ていると、留学生や帰国子女は積極的に授業に参加する一方、海外経験なしのチームは、積極的な発言はほとんどしない傾向にあります。
海外経験のない者は、英語を使うことに抵抗感があるようです。それはそうです。高校まではトップクラスの英語力の持ち主、「すごいなぁ」と周囲からちやほやされていた生徒が、突然、帰国子女や留学生の中に混じり「英語を使用」する場に放り出されて、戸惑うのも仕方がありません。
そんな学生たちも、週に5コマとか6コマのイマージョン式授業を受けながら、家庭で週に数時間から十数時間にも及ぶの大量の英文読解や英作文を課題としてこなしているうちに、いつしか実践に耐えうる英語力を身につけていくのです。
しかし、それでも3年生になっても4年生になっても、ついに英語を積極的に話すのは帰国子女や留学生ばかりで、純ジャパたちはあまり喋らない(←もちろん、中には賑やかなのもいますが)。その傾向はそのままなのです。
ここの部分、よろしいでしょうか?彼らは英語をあまり口にはしないけれど、英文を読んだり書いたり聞き取ったりできるのですよ。
いかがでしょう。日本式CLILでは、とにかく英語を「話す」ことが強調されますが、英語を身につけた人間たちは、英語を「話す」ことで英語を身につけたのではありません。彼らは自分自身を英語に「浸す(イマージ)」ことで英語が身につけたのではないでしょうか。「アウトプット」ばかり強調されているCLILですが、実は「インプット」こそが、CLILの本質なのです。
「英語で話せば~」の論理は、以前にも書いたところの「健康な人は風呂に入っていた」だから、「風呂に入れば健康になる」という理屈と通底しています。(パルキッズ通信2019年12月号『「インプット」で英語教育を考える理由』)
健康な人は、毎日ゆっくり風呂に浸かれる物理的設備も時間的・精神的余裕もあるから、それができるのでしょう。「風呂に入るか否か」という変数だけを見て、その他の「経済的あるいは精神的余裕」といった変数をあまり考慮せず、必要以上の重みをかけて「風呂」と「健康」を結びつけるのは少し乱暴だと思います。
「英語を口にするか否か」で「英語の習得の可否」を語るのも同様です。それ以外の「多読・多聴」といった、インプットに関わる変数にももっと目が向けられるべきだと思います。
最後に、日本人の英語学習に対するモチベーションについて
 古には生き残りのため、あるいは経済的な有意性を保つためというのが、外国語学習のモチベーションとなっていましたが、今日の平和な日本で学生たちは果たして英語学習に対してモチベーションを持っているのか、また持ち合わせているのならどのようなモチベーションなのでしょうか。
古には生き残りのため、あるいは経済的な有意性を保つためというのが、外国語学習のモチベーションとなっていましたが、今日の平和な日本で学生たちは果たして英語学習に対してモチベーションを持っているのか、また持ち合わせているのならどのようなモチベーションなのでしょうか。
ベネッセの中学生対象のアンケート結果や、信憑性はさておきその他ウェブ上で見かける「英語」と「モチベーション」の関係はざっと以下のようになります。
※()内は私の突っ込み。
まずは、
・「昇進・転職のため(つまりはTOEIC対策ね)」
これは生死には関わりませんが、立派なモチベーションです。しかし、その他はとなると心細い。
・「外国人と話がしたい(中国人や他のアジアの人たちじゃダメなの?)」
・「街で外国人を助けたい(困っている日本人を助ければ?)」
・「会話を楽しむ(日本語では会話は楽しめないの?)」
・「旅行で便利(それこそ通訳機で足りるのでは?)」
・「現地の人と交流できる(人と交流したいなら、日本の観光地でもOK?)」
・「視野が広がる(まぁ、確かに受け取れる情報の幅は広がります)」
・「洋楽や洋画を楽しみたい(これは文学的ですね)」
・「格好良い(う~ん・・・)」
最初の「昇進」云々以外には、古人の「生き残り」とか「経済的優位に」などのモチベーションの頑強さは微塵も感じられません。もちろん、仕事や研究で英語が必要な人たちはいますし、そんな人たちは何らかの方法で英語を身につけるのでしょう。つまり、モチベーションが十分強ければ、自然とそれを満たす環境に身を置く結果、英語を身につけるのです。
しかし、それ以外の大半の日本人にとっての英語は「できたらステキねぇ」という「あこがれ」程度の存在に留まっているようです。そして、これではモチベーションが弱すぎるでしょう。
冒頭でも述べましたが、日本人は今になっても、あまり英語を習得することに差し迫った意義を感じていないのです。
正しく実践すれば、CLILは効果てき面!
 最後の最後に、冒頭の①モチベーションと②方法に話を戻します。
最後の最後に、冒頭の①モチベーションと②方法に話を戻します。
一部を除き、日本人はそもそも英語習得に対する強烈なモチベーションを持ち合わせていない。つまり、①の不在。
それでも、留学生のように毎日英語漬けにされるか、あるいは留学しないまでも英語科の学生たちのように授業で7、8時間、課題に10時間、併せて週に15~20時間もイマージョン教育をすれば、それは正しい②の選択をしたことになります。胸を張って “CLILで英語を身につけたぞ!” と言えばよろしい。
しかし、現実には、留学や英語科などに属して “(ホンモノの)CLIL” を体験できる人は限られています(パルキッズ通信2020年1月号「留学生に起きた魔法を家庭で起こす」参照)。
そして、モチベーション不在のまま、彼らが体験するCLIL自体も日本の学校文化に調整されて、弱められてしまった “weak CLIL” なのです。
CLIL自体は、外国語習得の考え方として十二分に優れた概念です。私自身もあるいは上智に入ってくる学生たちも、留学先で、あるいは学内での徹底的なイマージョン教育によって知らず知らずのうちにCLILを実践したと言えます。
冗談抜きで「CLIL万歳」と叫びたい。現に『パルキッズ』シリーズもCLILですし、特に『パルキッズジュニア』に至っては “CLILの権化” と呼んでも良いくらいです。(←もうここまでくると、、、笑ってはいけませんが、CLILとは本当に便利・万能な言葉です)
大学ばかりでなく、高校や中学、さらには小学校にまでCLILが取り入れられようとしていますが、すでに海外でも ‘nominally(表面的な)” とか “guise(見せかけの)” などと揶揄されているようなCLILが横行しています。そのような中途半端なCLILでは、その成果の程はいかがなものなのでしょうか。
はてさて、ここは私の悪い予感が的中しないことを祈るばかりです。
【編集後記】
今回の記事をご覧になった方におすすめの記事をご紹介いたします。ぜひ下記の記事も併せてご覧ください。
★外国語習得に成功するたったひとつの方法
★「生活言語」と「学習言語」
★小学校英語。得する人と損する人
★だから英語がわからない!
【注目書籍】『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)
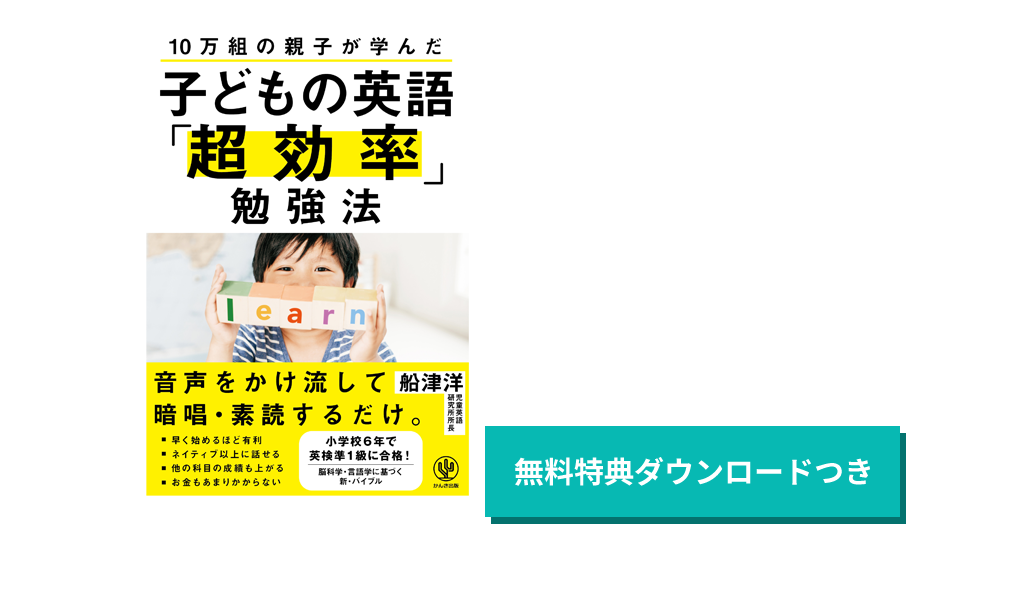 児童英語研究所・所長、船津洋が書き下ろした『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)でご紹介しているパルキッズプログラムは、誕生してから30年、10万組の親子が実践し成果を出してきた「超効率」勉強法です。書籍でご紹介しているメソッドと教材で、私たちと一緒にお子様をバイリンガルに育てましょう。
児童英語研究所・所長、船津洋が書き下ろした『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)でご紹介しているパルキッズプログラムは、誕生してから30年、10万組の親子が実践し成果を出してきた「超効率」勉強法です。書籍でご紹介しているメソッドと教材で、私たちと一緒にお子様をバイリンガルに育てましょう。

※本記事のテキストは引用・転載可能です。引用・転載する場合は出典として下記の情報を併記してください。
引用・転載元:
https://www.palkids.co.jp/palkids-webmagazine/tokushu-2005/
船津洋『”CLIL” って何? 効果あるの?』(株式会社 児童英語研究所、2020年)