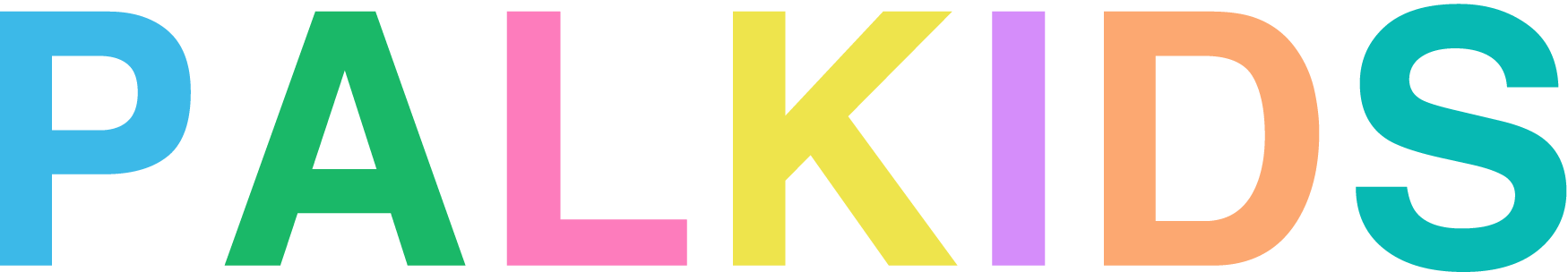パルキッズ通信 特集 | 大量インプット, 日本の教育, 早期教育, 英検対策, 言語獲得

2019年12月号特集
Vol.261 |「インプット」で英語教育を考える理由
「子どもの英語『超効率』勉強法」の発刊に当たり
written by 船津 洋(Hiroshi Funatsu)
※本記事のテキストは引用・転載可能です。引用・転載する場合は出典として下記の情報を併記してください。
引用・転載元:
https://www.palkids.co.jp/palkids-webmagazine/tokushu-1912/
船津洋『「インプット」で英語教育を考える理由』(株式会社 児童英語研究所、2019年)
「4技能」という言葉の罪
 「英語の4技能」という言葉があります。英語の運用能力を、読む・書く・聞く・話すという4つの側面から捉えた言葉で、それ自体には大した意味はありません。また、それらの側面を通して英語の力を測ることは別に悪いことではありません。
「英語の4技能」という言葉があります。英語の運用能力を、読む・書く・聞く・話すという4つの側面から捉えた言葉で、それ自体には大した意味はありません。また、それらの側面を通して英語の力を測ることは別に悪いことではありません。
しかし、ひとつ考え方を誤ると、とても罪深い言葉になってしまいます。今回の大学入試の英語に関わる外部試験導入のドタバタの根底には、この言葉に翻弄されている文科省の姿が伺えます。
少し考えてみれば分かることではないでしょうか。英語の4技能という言葉を「日本語の4技能」と置き換えてみれば、いろいろなことが見えてきます。
例えば、大学入試で「日本語の運用能力」を測ろうとするならば、まず日本語の理解力を問う必要があります。理解力には耳からの理解と目からの理解、つまり「聴解力」と「読解力」があります。ただこの両者は “1つの能力の2つの異なる側面” なので、純粋に「理解力」を測定するならば「読解力」のみ測れば十分です。
さらに受験者の「思考力」つまり物事をどのように捉え、どのような思考をするのかを問いたければ「小論」を書かせれば良いわけです。あるいは「面接」を通して口頭で思考力を問うことも可能です。
しかし、国語に関しては、ほとんどの大学で「読解力」で「理解力」のみが測定されているのが現状です。
なぜでしょう。
国語も英語も「読解力」のみで大体測定出来る
 いろいろ理由はあると思います。小論や面接は、実施が「たいへん」である点が1つでしょう。また、評価者によって多かれ少なかれ採点に「バラツキ」があることは避けられません。時間や人件費などのコストや、結果判定の質の問題を考えれば、「リスクの高い」思考力の判断(書く・話す)はとりあえず棚上げして、理解力(特に読む)のみで受験者の日本語の能力を測定するのは、極めて「健全な思考」の行き着く先でしょう。
いろいろ理由はあると思います。小論や面接は、実施が「たいへん」である点が1つでしょう。また、評価者によって多かれ少なかれ採点に「バラツキ」があることは避けられません。時間や人件費などのコストや、結果判定の質の問題を考えれば、「リスクの高い」思考力の判断(書く・話す)はとりあえず棚上げして、理解力(特に読む)のみで受験者の日本語の能力を測定するのは、極めて「健全な思考」の行き着く先でしょう。
「理解力」と「思考力」は別の能力ではありません。「理解力」が優れている人の方が思考も深くなります。しかし、優れた思考力を持っているにも関わらず、理解力がないという人は考えられません。つまり、理解力と思考力は「理解力」が先行して、それに「思考力」が追いついていく、という関係にあります。
「理解力」>「思考力」。こんな図式です。
この点からも、大学入試の国語では「理解力」のみを問うことに、一理ありそうです。
英語も国語と同じく言語ですから、この考え方は英語科にも当てはまります。英語の「理解力」が測定できれば、その学生の英語力自体を “推測” することができます。
例えば、英語の読解問題で100点取れる学生の方が、50点しか取れない学生よりも英語の「理解力」が高いことは当然ですが、同時に一般的に英語での「思考力」も高い傾向にあることは間違いないでしょう。
この点から、大学入試の英語では「読解力」、つまり「理解力」のみを問うているケースが圧倒的に多いのです。そして、必要に応じて2次試験でリスニングを課して「聴解力」を計測したり、小論や面接で「思考力」を測定していれば十分だったのです。
それでうまく行っていたのです。
指導要領に書いてあるから・・・
 ところが、ここに「4技能」という言葉が登場します。しかも、誰が唱え出したのか「4技能をバランス良く」という、一見すると一理ありそう、しかし、よく考えれば大学受験とはあまり関係のない言葉が、あちらこちらを引っかき回すこととなります。
ところが、ここに「4技能」という言葉が登場します。しかも、誰が唱え出したのか「4技能をバランス良く」という、一見すると一理ありそう、しかし、よく考えれば大学受験とはあまり関係のない言葉が、あちらこちらを引っかき回すこととなります。
今回の騒動。なぜ、こんなことになったのでしょうか。答えは簡単、それは「学習指導要領に書いてあるから」です。
グローバル化やIT技術の進歩によって、世界が小さくなり、同時に商圏にも国境がなくなりつつあります。そんな中、日本人は「リンガフランカ」としての英語での情報のやりとりが苦手です。英語の論文が読めなければ、最新の学問は手に入りません。逆に、どれほど優れた研究成果でも、英語で発信できなければ、それは英語中心の世界の中においては「存在しない」に等しいのです。
この意味では、最新研究や専門性の高い学問の世界においては、英語の運用力の向上は喫緊の問題であることは間違いありません。また、ビジネスの世界においても、国際社会を舞台に活躍できる、つまり主に英語を使いこなせる人材を求める傾向は高まっています。
このような背景から、文科省が英語教育に力を入れるのは、国策として当然のことと言えます。
しかし、なぜ4技能なのでしょうか。
なぜ指導要領に盛り込まれたのか
 大きな疑問は2つです。1)日本人の英語力の向上がなぜ4技能と結びつくのか、2)なぜ大学入試で4技能を測定しなくてはいけないのか。
大きな疑問は2つです。1)日本人の英語力の向上がなぜ4技能と結びつくのか、2)なぜ大学入試で4技能を測定しなくてはいけないのか。
1番目の問いにひと言で答えれば、それは「指導要領に書いてある」からです。一連の英語教育改革の流れの中で、従来の文法・訳読方式への反省が強く打ち出され、それが「日本人の英語下手」の主犯扱いされた嫌いがあります。
そして、その「悪役」に対する正義の味方、実際に「使える英語」の象徴として、「聞く」「話す」が登場します。
さらに、指導要領に英語の「思考力・判断力・表現力」を育てることが盛り込まれたことから、さらに「話す」と「書く」にスポットライトが当たります。
それを応援するサイドキック(バットマンのロビンやホームズのワトソン)としてCEFR(ヨーロッパにおける外国語の能力の共通の指標)という強い?味方が登場します。
余談ですが、ヨーロッパの言語において、ロマンス語(仏・伊・西など)は兄弟みたいなものですし、ロマンス語とゲルマン語(英・蘭など)も従兄弟のような関係なので、その指標を日本語にとっての英語という「赤の他人」に適用するのはいかがなものかと思います。
現に、日本人の英語力はCEFRの6段階(低い方からA1~C2)の中のA1、つまり最も下のレベルに集中しているので、統計的にはフロア効果をもたらす、あまり優れた指標でないことは明らかです。
いずれにしても、英語教育改革のこのような流れから「4技能」しかも、読解中心ではなく、聞く・話す・書くもちゃんと取り入れた「4技能バランス良く」という考え方が自然発生してきたわけです。
英語が出来る人は4技能バランス良く身につけている?
 それでも「4技能」と「英語力向上」との結びつきはよく分からないままです。
それでも「4技能」と「英語力向上」との結びつきはよく分からないままです。
しかし、専門家は「英語での活動(聞く・話すなど)を楽しいと感じる子の方が英語力が高い」ので「英語での活動をすれば英語力が上がる」などと話します。
この考え方は、僕のような者には「健康な人は風呂に入っているようだから、健康になるために風呂に入ろう」といった考え方と同じように映ります。あるいは「英語ができる学生は4技能共に優秀だ」だから「英語優秀者に育てるためには4技能の訓練をすれば良い」と聞こえてしまうのです。
「毎日ゆっくり風呂に入れるような時間的・精神的余裕がある人は、そうでない人に比べればストレスが少ないので健康である」でしょうし、「英語ができる人は結果として4技能ができる」わけであって決して「その逆は然りではない」という根本的なロジックがすっぽり抜け落ちてはいないでしょうか。
この点に関しては、もう少し後で、もう少し詳しく述べます。
いずれにせよ、そんな「4技能ロジック」に「とりあえずやってみよう」的な「CLIL(内容言語統一型学習)」、つまり英語自体を学ぶのではなく、内容(テーマ)に関して英語でやりとりする中で、英語も身につけていくという考え方がドッキングして現在の学習指導要領となっています。
しかも、もうそこに書かれてしまっているのですから、処置なしです。
今回の騒動のまとめ
 そのような経緯から「4技能バランス良く」勉強しましょうねとなっているようですが、これが大学入試と何の関係があるのでしょうか。
そのような経緯から「4技能バランス良く」勉強しましょうねとなっているようですが、これが大学入試と何の関係があるのでしょうか。
国策として日本人の英語力を底上げすることには大いに賛成です。しかし、それが「4技能」を通して、となるとまったく賛成しかねますが、それでも決まってしまったことは仕方がありません。しかし、それが大学入試にも影響してくるとなると、これは大問題です。
当の受験生やその保護者の皆様にとっては、切実なる思いをお持ちでしょうし、高校の英語科や進路指導などにも大きく影響しているので、現場の皆様のご心労は察して余りあるところです。そして結局、2020年の外部試験導入は先送りされました。
しかし、なぜ文科省はこれほどに導入を急いだのでしょう。
その前に、今回の騒動と外部試験に関して整理すると以下のようになります。
まず全体として、「思考力・判断力・表現力」は英語に限ったことではないので、英語以外の国語や数学などの試験にも論述問題が課されることになります。そこにはすでに述べたように採点者の判断のバラツキをはじめとした「高いリスク」があります。
これも、判定側の企業が対策問題集を作るなどの問題点が、すでにニュースとなっています。ただ、こちらは強行されるようです。(この記事が書かれた2019年11月時点 : その後12月6に批判の多い国数の記述問題に関しても政府は延期の検討にはいっています。:12月12日段階で国数の記述も見送る決定が成されたようです。)
その次の次元に、大学入試の英語に限ったイシューがあります。こちらの要点は、1)大学入学共通テストでの筆記・リスニングの配点の変更、2)外部試験導入に関わる課題、です。
このうちの1)は予定通り行われます。従来のセンター試験では、筆記200点に対してリスニングは50点でした。4:1だったわけです。これが1:1になります。リスニングの得意なパルキッズたちには朗報ですが、リスニングが苦手な平均的な学生たちにとっては「お気の毒さま」です。しかし、決まってしまったのですから仕方がありません。
そして、2)の外部試験の正式導入が先送りされたわけです。つまり、文科省は「4技能」で測定するのを当面は諦めて「話す・書く」試験を一時的にせよ先送りしたということです。
ただ、もともと大学には独自の教育や入学試験を行うことが期待されています。さらに私立大学ともなれば、一層独立した理念のもと研究・教育が行われることが健全です。
東大が外部試験の導入について、反対、賛成、そして反対と二転三転したことが取り上げられますが、私立大でも対応は分かれています。慶應義塾のように我が道を行く大学もあれば、上智(実は4技能の言い出しっぺ)のように2020年度からは英語の独自試験を廃して全て外部試験に移行すると打ち出している大学もあります。
そこに「これ」ですので、すったもんだの大騒ぎです。文科省に素直に従ってきた大学は、上ったはしごを外された形です。
ただ、外部試験の導入は各大学に委されているので、文科省が先送りしようがすまいが、利用するところは英検をはじめとした外部試験を利用すれば済むわけです。ただ、大学入試センターが一括して学生の成績情報を大学側に提供する仕組み(仲介者)が消えてしまったので、今後は成績のやりとりが学生と学校の直接のやりとりとなるという、大きな課題を残してしまった形です。
なぜ大学入試に4技能?
 ところで、そもそもなぜ大学入試に「4技能」なのかという疑問はまだ解決されていません。
ところで、そもそもなぜ大学入試に「4技能」なのかという疑問はまだ解決されていません。
英語での「思考力・判断力・表現力」向上は日本人全体に課されても良いと思いますが、大学入試とは別の話でしょう。
そもそも、すべての高校生が大学に進学するわけではありません。またすべての大学生が、英語の運用力がクリティカルな英語科・英文科・国際教養学部などに進むわけではありません。国文なら英語より古文や漢文の読み解き、哲学科ならドイツ語やラテン語など英語とはまったく縁のない学部学科もあるわけです。
そこに、一律に「大学入試」のお題目の下、英語の「4技能」を当てはめる。
この理由は衝撃的でした。
どうやら「中・高で4技能バランス良く指導させるためには、大学入試で4技能を取り入れるのが良い」という判断が働いたようなのです。つまり、放っておくと「指導要領」に沿った指導が現場で行われない可能性があるので、「大学入試」を持ち出したということのようです。大学入試に必要ならば、中・高で取り組まざるを得ないだろう、ということでしょうか。
私は教育改革・行政の専門家ではなく、一介のビジネスマンですので、このあたりの因果関係は理解できませんが、どうも「理想論」あるいは「あるべき論」が一人歩きをしているとしか、私の目には映らないのです。
本質は全く別のところに
 以上が「英語」と「4技能」を取り巻く今回の騒動の、私なりの理解です。
以上が「英語」と「4技能」を取り巻く今回の騒動の、私なりの理解です。
しかし、「4技能」も「外部試験」も本質にはまったく届きません。本質とは、つまり「日本人の英語力を向上させること」です。
すでに述べたように「英語ができる学生は4技能共に優れている」あるいは「英語のできる学生は英語での活動が好き」だから、「4技能バランス良く取り組む」また「英語での活動をふんだんに取り入れる」ことで「英語力を上げる」という発想自体にそもそも問題があると考えます。
真摯に向き合うべきは「英語のできる学生」は「何をしたから英語が身についたのか」、「英語を身につけられない学生には足りない」その「何か」を突き詰めるべきではないでしょうか。
英語の授業のコマ数は、昭和の時代から倍増しています。
「それが重要」と叫ばれている「英語での活動」には、昭和の時代では考えられないほど多くの時間が割かれるようになっています。
しかし、聞こえてくるのは「アジアで最下位の英語力」「英語での発信力が足りない大学」などのニュースばかりです。ゆとり教育と共に始まり、年々低年齢化している学校英語ですが、20年ほど経った現在、つまり今のアラサー世代以降の英語力がめざましく上がったという話は聞きません。
ビジネスマン的な発想でいけば、これは「失策」。そして「失策」であれば早期に「撤収」することが、傷口を広げない防衛手段です。
まぁ、行政はビジネスではないので、鶴の一声で、というわけにはいかないのでしょうが…。
それでは、英語力涵養に繋がる本質はどこにあるのでしょうか。
それは「インプット」にあると考えられます。
「インプット」のフィルターを通して広がる景色
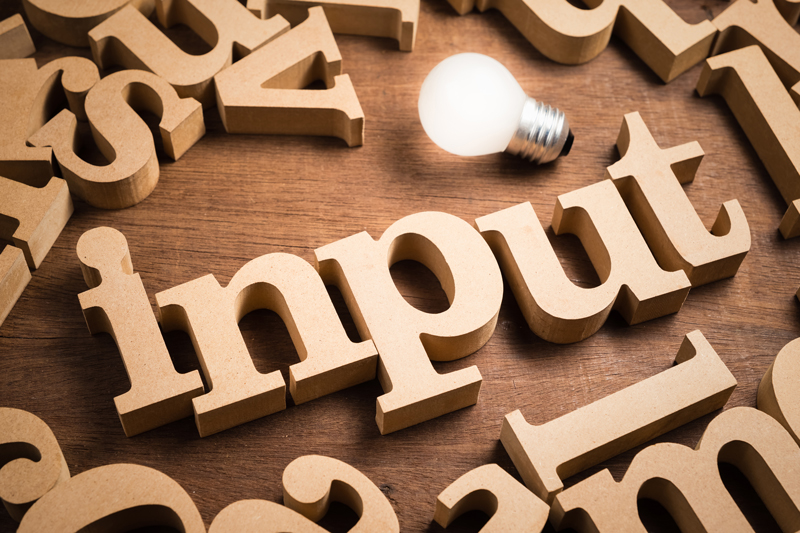 個人的には、外国語習得を語る資格のある人間は、実際に外国語習得で苦労した経験のある人間だと考えています。
個人的には、外国語習得を語る資格のある人間は、実際に外国語習得で苦労した経験のある人間だと考えています。
幼児期や小学生の早い時期までに英語を身につけてしまった人間は、外国語習得に「イヤな思い」を抱いたことや「辛い経験」をしたことはあるかも知れませんが、「どのようにして」自分が英語を身につけたのかを内省することができません。
私たち日本人は、幼児期に日本語を身につけてしまっているので、どのようにして日本語を身につけたのかが分かりません。幼少期に日本語と英語を身につけてしまったバイリンガルも同じです。気付けば日本語も英語も使えるようになっているので、「英語ができなかった自分」と「英語が分かる自分」を橋渡しする「何か」に迫ることができないのです。
その点、苦労してバイリンガルになった、あるいは苦労しないまでも、思春期よりあとにバイリンガルになった人たちは、「英語ができない自分」を知っています。
そんな人たちに「言語学」、「言語心理学」、「第二言語習得論」などの知識が加わってこそ、「できない」と「できる」のその間にある「何か」に迫ることができると思います。
その意味では私自身、高校時代の交換留学で英語を身につけた一人なので、この点に関して語る資格があると思っています。
さらに、数多くの親子に接しつつバイリンガル教育を現場で実践してきた経験からも、その「何か」にはかなり近いところにいると勝手に思っています。
そして、私なりに考察するに、英語ができる人とできない人を隔てる「何か」、英語ができる人は必ず経験してきた「何か」とは「インプット」であるとの結論に到達したのです。
「インプット」>「アウトプット」の関係
 インプットとアウトプットの関係は、すでに触れたところの「理解力」・「思考力」の関係とも通じています。また「知覚(受信)」・「産出(発信)」とも同様の関係にあります。
インプットとアウトプットの関係は、すでに触れたところの「理解力」・「思考力」の関係とも通じています。また「知覚(受信)」・「産出(発信)」とも同様の関係にあります。
つまり、まず「知覚」「受信」「理解」など「インプット」に関わる能力が発達し、それに続いて「産出」「発信」「思考」など「アウトプット」に関わる能力が育っていくのが、ものの順序です。
いきなり英語で思考したり、発信したりなどできるはずもありません。
そんなことをするとどうなるのでしょうか。
My skin is naive. (私の肌は世間知らずです:通常naiveは否定的な意味で使われます)
I want an open car. (私はドアの開いている車が欲しいです:cf. convertible)
Maybe, I can don’t study math. (意味不明)
My sister is influenza. (私の妹はインフルエンザです:「それ自体」という意味になります)
英語が分からない、そんな状態で英語で発信しようとすると、こんな事態になるのです。このような例は、街中にあふれています。”Engrish in Japan”(←スペル間違いではありません)で検索すれば、街中にあるこうした無数の「奇妙な英語」をみることができます。仮にこれらが奇妙であっても、意味が通じれば良いのですが、まるで意味が通じないとなると、このようなアウトプットにどんな意味があるのか、極めて疑問です。
しかし、「文法など気にせず、とにかくアウトプットしてみようよ」と専門家が言うのですから、彼らが果たして「文法を気にせず英語で話した結果どうなるのか」を理解しているのかはなはだ疑問です。
まずは、正しい英語の回路を身につけ「インプット」つまり、英語を理解することができるようになって、その後に「アウトプット」で自分の考えを英語で発信できるようになる。これがまっとうな順序ではないでしょうか。
このように順序的には「インプット」が「アウトプット」に先行するのですが、同時に能力的にも「インプット」の方が「アウトプット」より優れているのが自然です。
小説を読んで楽しむ、つまり「インプット」は多くの人が楽しむことができますが、その小説を0から生み出す「アウトプット」までもできる人は少数派です。要するに、言語の能力において「アウトプット」が「インプット」より優れている人など存在しないのです。
この意味でも「インプット」の重要性がご理解いただけるでしょう。
そして、繰り返しになりますが、英語を身につけたいのであれば、「アウトプット」の練習ではなく「インプット」が重要であることも、直感的にご理解いただけると思います。
「インプット」には「正しい方法」「適切な質」「十分な量」の三大要素が重要
 なぜ「インプット」から英語が身につくのかという詳細はここでは省きますが、我武者羅にインプットすれば良いというわけではありません。
なぜ「インプット」から英語が身につくのかという詳細はここでは省きますが、我武者羅にインプットすれば良いというわけではありません。
なぜなら、いくらインプットしたつもりでも、まったくインプットにならないことが少なくないからです。
インプットの方法は2つに大別できます。ひとつは耳から、もうひとつは目からです。
このどちらかを好みで選べば良い、あるいは両方すれば良い、というものではありません。
年齢、発達段階、言語能力に応じて、インプットの方法を選択する必要があるのです。
大人になってしまうと、英語を耳からインプットすることはできません。
人間の脳には、経済性理論が働いていて、脳は「ムダだ」と判断した作業を行わないのです。例えば、日本人は生後10ヶ月ほどで日本語の音をマスターします。すると、英語の音には興味を示さなくなります。
もちろん、留学をはじめとした英語漬の環境を作り出せば、脳は「必要な情報」として英語を処理し始めますが、そのスイッチを入れるのは大変な作業です。従って、日本人の脳は日常的に「英語は不要」として聞き流してしまうようにできているのです。
そこに、いくら英語を聞き流しても、それは処理されないので、雑音として右から左へと抜けて行ってしまいます。つまり、インプットになりません。
それでは、目からのインプットはどうなのでしょう。目からのインプットの代表は「多読」でしょう。しかし、その多読も実はインプットにはならないのです。
実際に多読を体験された方もいらっしゃるかも知れませんが、数ページで投げ出してしまったり、投げ出さなくても、辞書を引き引き、1冊の本を読むのに1年かかってしまったり、などということはありませんでしょうか?これでは多読にはなりません。
多読は、ある程度以上の英語力を身につけた人が取り組むべき作業であって、英語を身につける途上の人が多読をしても、それは「ストレス要因」にしかなり得ないのです。
つまり、いくら英語を聞き流しても、いくら英文を読んでみても、脳が処理してくれなければ、英語の「インプット」にはならないのです。
インプットの方法はその情報が「インプットされる」ことを前提に決定する必要がありますが、それは「既知の情報+1(新刊参照)」が適切であって、それ以外の方法は逆に避けるべきです。
適切な質と十分な量
 続いて必要なのが、質と量の確保です。
いくらインプットしても、その質が劣っていては「間違えた入力」となってしまいます。
続いて必要なのが、質と量の確保です。
いくらインプットしても、その質が劣っていては「間違えた入力」となってしまいます。
ゴルフには「正しいスウィング」と「間違えたスウィング」しかないと言います。間違えたスウィングを反復することによって、それは間違えたインプットとなり、結果として、間違えたスウィングが習慣付いてしまいます。これを訂正するのは、並大抵なことではないそうです。
それであれば、最初から自己流を避けて、プロについて練習するのが費用対効果が高いことは言うまでもないでしょう。
つまり、「適当な質」の「インプット」でなければ意味がないのです。
また、量に関しても、少量の入力では一向に英語が育つことはありません。
我々の中学生向けのレッスンでは、1日に2.5万語を読ませます。2.5万語のインプット、これは一般的な中学校の教科書の10年分に相当します。学校英語が、いかに「インプット」を軽視しているのか、この1点のみでも分かります。1時間ほどで読める内容に3年です。
人の脳は言語をマスターできるように作られています。もちろん、幼児期にその能力が優れていることは言うまでもありません。しかし、幼児期を逃しても、例えば高校での留学生のように、英語をマスターすることはできるのです。
しかし、そのためには脳が英語の音や文の配列の規則を分析するに「十分な量」の英文を「インプット」する必要があるのです。
はじめに、に代えて
 このたび、拙著『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)が発売となりました。
このたび、拙著『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)が発売となりました。
この本は、上記のような「現在の日本の英語教育」への無力感と同時に、「一人でも多くの人に英語を身につけてもらいたい」という一筋の希望の意味を込めて書き下ろしました。
「英語を身につけることなど簡単なのです。」
「人は英語を身につけられるように生まれてきているのです。」
「英語を身につけるには正しいインプットが必要なのです。」
この本では、具体的な成果として “とりあえず”「英検準2級」から、「英検準1級」を目指した英語力の育て方を書き綴っています。
年齢と英語力にあった、「正しい入力方法」「適当な質」「十分な量」の「インプット」を年齢別に示してあります。
さらに、子どもたちの英語の発達と英検のレベル感も分かりやすく解説しています。
本書は以下の6つの章から構成されています。
プロローグ 子どもの英語はなぜ身につかないのか?
第1章 英語教育を早く始めることで手に入るメリットとは
第2章 子どもの英語「超効率」勉強法・基本編
第3章 子どもの英語力の目安になる「英検のレベル感」とは
第4章 幼児期から始める英語「超効率」勉強法
第5章 小学校低学年から始める英語「超効率」勉強法
第6章 小学校中学年以上から始める英語「超効率」勉強法
実はこの他に、編集の都合上泣く泣くカットとなった第7章が存在します。そこでは「英検の筆記対策の裏技」を公開しています。この章には、本書の巻末から「読者プレゼント」としてアクセスできるようになっています。
一人でも多くの皆様が本書を手にとってくださり、それにより一人でも多くの子どもたちが「英語で苦労する負のスパイラル」から抜け出していただくことを心より願っております。
【編集後記】
今回の記事をご覧になった方におすすめの記事をご紹介いたします。ぜひ下記の記事も併せてご覧ください。
★パルキッズで育つ子の英語力の本当のところ
★英語の育て方
★外国語習得に成功するたったひとつの方法
【注目書籍】『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)
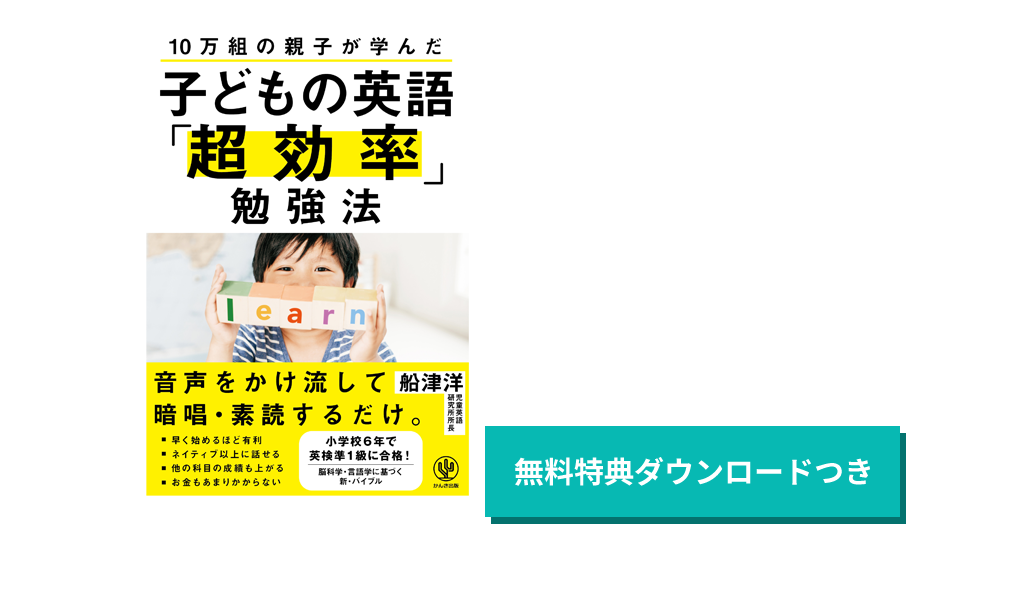 児童英語研究所・所長、船津洋が書き下ろした『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)でご紹介しているパルキッズプログラムは、誕生してから30年、10万組の親子が実践し成果を出してきた「超効率」勉強法です。書籍でご紹介しているメソッドと教材で、私たちと一緒にお子様をバイリンガルに育てましょう。
児童英語研究所・所長、船津洋が書き下ろした『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)でご紹介しているパルキッズプログラムは、誕生してから30年、10万組の親子が実践し成果を出してきた「超効率」勉強法です。書籍でご紹介しているメソッドと教材で、私たちと一緒にお子様をバイリンガルに育てましょう。


船津 洋(Funatsu Hiroshi)
1965年生まれ。東京都出身。株式会社児童英語研究所・代表取締役。上智大学外国語学部英語学科卒業。実用英語技能検定1級取得。30年以上に渡る幼児教室・英語教室での教務を通じて幼児の発達研究に携わるかたわら、「パルキッズ」などの英語教材を始めとした幼児向け教材を多数開発。また、全国の幼児・児童を持つ親に対して9万件以上のバイリンガル教育指導を行う。講演にも定評があり、全国各地で英語教育メソッドを広めている。著書に20万部のベストセラーを記録した『たった80単語「読むだけで」英語脳になる本』(三笠書房)をはじめ『どんな子でもバイリンガルに育つ魔法のメソッド』(総合法令出版)『ローマ字で読むな!』(フォレスト出版)『英語の絶対音感トレーニング』(フォレスト出版)など多数ある。