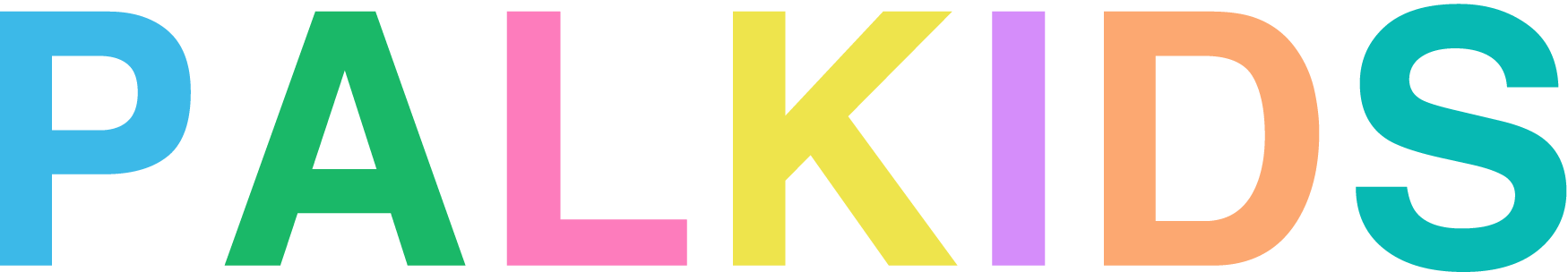パルキッズ通信 特集 | 大量インプット, 子供の成長, 発音, 言語学, 言語獲得
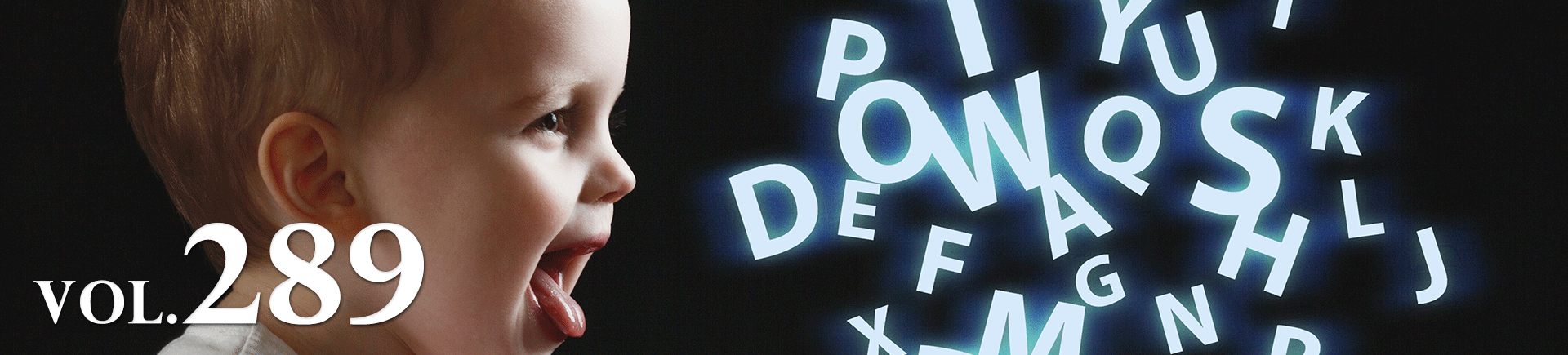
2022年4月号特集
Vol.289 | 伝わる英語を話せる人とそうでない人
パルキッズたちは、なぜ英語の発音が良いのか?の「謎」にせまる
written by 船津 洋(Hiroshi Funatsu)
※本記事のテキストは引用・転載可能です。引用・転載する場合は出典として下記の情報を併記してください。
引用・転載元:
https://www.palkids.co.jp/palkids-webmagazine/tokushu-2204/
船津洋『伝わる英語を話せる人とそうでない人』(株式会社 児童英語研究所、2022年)
共感力に優れているヒト
 人間はもともと共感する力を持っています。
人間はもともと共感する力を持っています。
「それが英語とどんな関係があるのか」という声が聞こえてきそうですが、実は大ありなのです。
「ミラーニューロン」ということばを聞いたことがありますでしょうか。例えば、誰かと話をしているときに、無意識のうちに相手と同じポーズを取っていることはありませんか。これは「相手のしていることを自分のしていることのように感じてみる」というミラーニューロンの働きによるそうです。
私の頭の中では「まだ英語と関係なさそうじゃないか」という声が聞こえていますが、この一人突っ込みもミラーニューロンのなせる技かも知れません。
「相手に共感する」「相手を慮る」こと。
これは日々の会話で常に行われています。日常会話にて話し手の口から出てくることばは、例えば次のようなものです。
「ほら、もう8時(幼稚園や学校に出かける時間)よ。」というと、これを聞いた子どもたちはどうしますか。おそらく、そそくさと出かける準備を始めることでしょう。発話の意味は単に時間を告げているだけです。もちろん、子どもたちはその字義通りの意味を理解しています。その上で、母親の発言から言外の意味、つまり「出かける準備をしなさい」というメッセージを読み取って、そのメッセージに合意しつつ、それなりの行動を取り始めるのです。
「晩ご飯できたよ」と言われれば、それを単なる「晩ご飯の準備ができた」というメッセージと理解した上で、言外の意味である「食卓に来なさい」を理解して、そのメッセージに従います。
これは家族のように血のつながりがある近親者間でのみ起こる、つまり相手の言わんとすることを理解できる間柄だから起こることではありません。職場の同僚や友人との会話でも常に、「相手の言わんとすることを慮って、メッセージを深読みする」作業が行われています。
話の受け手側も、いざ聞き手に回ると、同じように言外の意味を含んだ発話をします。例えば、「明日、映画見に行かない?」に対して「明後日レポートの提出期限なんだ」と答えれば、そのメッセージの聞き手(つまり誘った人)は字義通りの意味を理解した上で、「ナルホド、それでは映画には行けないな」という言外の意味をくみ取ります。
このようにして、私たちの日々の言語使用は、常に相手との共感(もちろん共感しない人もいるでしょうけれども)をベースに成立しています。
さて、人間は協力し合う生き物であり、そもそもミラーニューロンなどという神経細胞を生まれながらに持っていることによって、相手と共感 ‘してしまう’ 性に縛られているのです。
そして、この人間の性が言語の習得にも一役買っているのです。
猿真似ではうまく行かない
 米国への留学生は半年もすれば、現地の英語を聞き取ることができるようになり、留学先である南部なら南部の訛りで、中西部なら中西部の訛りで英語を話すようになります。幼児たちが習得する日本語も同様で、親が日常話すような語彙やスタイル、あるいはアクセントで、子どもたちも日本語を話すようになります。
米国への留学生は半年もすれば、現地の英語を聞き取ることができるようになり、留学先である南部なら南部の訛りで、中西部なら中西部の訛りで英語を話すようになります。幼児たちが習得する日本語も同様で、親が日常話すような語彙やスタイル、あるいはアクセントで、子どもたちも日本語を話すようになります。
我がことを振り返ってみれば、恥ずかしながら若者に混じって英語で授業を受けているうちに、どうにも若者が喋るような口調を知らず知らずのうちに真似ていることがあります。彼らの口調を「真似る」というよりは、正確には彼らの口調に「寄せる」感覚です。50過ぎのおじさんが、ハリウッドの青春映画に出てくる若者のような、語尾を上げる口調で話しているのを想像するだにおぞましいことです。
しかし、これも遺伝子のなせる技です。教授と学生など「立場」が違えばそれなりの社会的なステータスに見合った話し方になりますが、こちらも学生。つまり、若者たちと同じ「仲間」であるという社会ステータスなので、話し方が彼らに寄らないようにすること自体が、人間の性に反していることになるのかも知れません。
ところで、留学生は留学先のそれぞれの地域のバラエティーのことばをマスターするのですが、どのように習得するのでしょうか。双子の兄弟でも、一人はアラバマに、もう一人はアイオワに留学すれば、二人の話す英語はそれぞれ南部とGA(北米標準)に分かれます。
高校で留学するのであれば、米国内なら、それ程文化の差はないでしょう。もちろん、語彙も文法も同じです。ただし、ひとつひとつの語の発音やアクセント、あるいは文のイントネーションはそれぞれ方言で異なります。つまり、双子の兄弟は “同じ米語” の “異なるバリエーション” を身につけることとなるのです。
さて、それでは、このように周囲の人間が話すことばの「音」「アクセント」「イントネーション」を、学習者はどのようにしてに身につけていくのでしょうか。まず、「音」と「アクセント・イントネーション」に分けて考えることにします。
アクセントやイントネーションに関しては、何となく真似ることもできると考えるかも知れませんが、実は、これがなかなかに難しいのです。関東方言話者が京阪方言を、その特徴だけで真似てみても、うまく行かずに先方に違和感を与えるのは日常のことです。(その点、谷崎潤一郎は尊敬に値するのかも知れませんが、私は京阪方言の母語話者ではないので、彼の評価はできません。)
私も関西へ行くと、どうしても関西人の話し方に寄せてしまうのですが、恥をかきたくないので、現地ではなるべく関東方言で通しています。もちろん、それでも学生たちに対して青春ドラマ調に話すのと同様に、無意識のうちに「寄せて」しまうのまでを制御するのは、なかなかに大変なことではあります。
いずれにしても、単に真似るだけではうまく行かないようです。
それでは次にもうひとつの「音」の方に目を向けてみましょう。
モーター理論
 「ヒトはどのように音素を身につけるのか」音声学の世界では、これは重大な問題のひとつです。
「ヒトはどのように音素を身につけるのか」音声学の世界では、これは重大な問題のひとつです。
タ行のイ段とウ段は、タ行の音ではありません。それぞれチャ行とツァ行の音となります。念のため、ヘボン式アルファベットで書いておきましょう。
「たちつてと」と続けて言うと、それぞれ ‘ta chi tsu te to’ となります。念には念を入れて音声記号で書くと[ta] [tɕi̥] [tsɯ] [te] [to] となります。巻いたしっぽのついている ‘c’ は、仮名で言うと「シ」の音でそれと [t] がくっついて「チ」となります。 ‘m’ がひっくり返っているのは日本語の「ウ」の音の特徴(異論もあります)です。英語の [u] は唇が丸くなるのに対して、日本語はあまり唇を使わずに発音します。母音の下の小さい丸は声帯が震えていないことを意味する印です。(気になる方はこちらで確認してください。
私たちは、タ行はタ行でひとかたまりで知覚します。少なくとも仮名を覚えたあとの子どもたちはタ行を1つのグループだと見なします。ところが、実際には子音の種類は3つあるわけです。ちなみに、ハ行は数え方によっては4つの異なる子音で成り立っています。
また、男性と女性では声の周波数が違います。男性が100Hz前後に対して、女性は200Hz前後の基本周波数(1秒間に声帯が震える回数)を持っています。子どもたちはだいたい300Hzです。さらに同じ人でも声を高くしたり低くすることで周波数は変化します。
つまり、男の人が「たちつてと」というのと、女の人が言うそれは周波数が異なり、同じ一人の人でも異なる周波数で発音するのです。込み入った話は避けますが、母音の周波数もそれぞれヒトによってパターンが異なります。老若男女、あるいは同じ人が口にする「はひふへほ」は、ひとつとして同じものはないのです。
しかし、私たちはそれを「はひふへほ」と聞き取ることができます。どうしてでしょう。
言語学における「モーター理論」では、「聞き手は耳にする音を無意識のうちに自分の中で再現している」ようなのです。実験では、人の話を聞きながら実際に聞き手の舌が、音をなぞって動いているのも確認されているのです。
つまり、ヒトは耳にした音を実際に口の中で再現することで、それに似せた音を出そうとしているのです。
いかがでしょう。目の前にいる相手と同じ姿勢を取ってしまうどころか、相手の口の中の動きまで再現しようとしている。我々人間には驚くべき共感力が備わっていると言えるでしょう。
関東人が関西方言を真似てしまう、年寄りが若者の中に混じるとそちらの口調に寄ってしまう。すべて無意識の人間の性のなせる技なのです。そして、このヒトの性が特に「音」の習得を中心に、アクセントやイントネーションを含む言語の習得に強く関係しているのです。
それでは、どのようにしてそのヒトの性が外国語の発音と関係しているのかを見ていくことにしましょう。
話すのは分かってから
 留学生の話をしましょう。
留学生の話をしましょう。
日本には「英語を話すことが英語習得に繋がる」という誤った認識が跋扈しています。この考え方はもはや遺伝子レベルに組み込まれているのではないかと訝りたくなるほど深く根を下ろしていて、ちょっとやそっと説明しても、この「信念」を曲げない人が珍しくありません。
その考えを敷衍して「日本の高校生は英語を話さないから英語で話せない」とか、「英語で文章を書かないから英文を書けるようにならない」などということが、専門家の口から出てくるのには驚きを隠せません。
そして、こう続きます。「英語を話す授業を増やせば英語が話せるようになる」あるいは「書かせる授業で書けるようになる」という具合です。この点に関しては、英語の4技能の記事(『パルキッズ通信2019年12月号』)で特集しているので、詳しくはそちらをご参照いただくとして、この「話せば身につく」式のロジックは、素人が常識で考えても「英語という複雑な言語体系を身につける方法」となり得ないことは明白でしょう。
もちろん、「英語で話すこと」は、英語力を「向上させる」のには大変有用です。また、英文を書くことも英語力を「伸ばす」原動力になります。しかし、ここで話しているのは「英語を身につけること」です。英語を聞いて十分に理解して、さらに十分相手に伝わる英作文をした上で、英語として十分な発音やリズムを身につけることです。無闇に「話すこと」「書くこと」に力を入れても、正しくない、あるいは間違えた英文を大量に産出するばかりで、「知覚」つまり聞き取ったりスラスラ読み込んだりする能力は一向に身につかないのは自明です。
私自身、留学生でしたので、自らの体験も踏まえて、話を進めましょう。
しばしば日本人は「シャイだから」あるいは「控えめだから、英語を話せるようにならない」と聞きます。まぁ、それが上の議論に繋がるわけです。しかし、実際そうなのでしょうか。はなはだ疑問です。
確かに、僕自身高校2年生の夏に渡米した当初、ホストファミリーともほとんど喋ることはありませんでした。話をしようとはするのですが、なかなか伝わらない。受け入れ先の家族も気を配って積極的に話しかけてくれるのですが、なかなか話が成立しない。
これは、僕がシャイだったからとか、控え目な性格だからという理由ではありません。ちなみに、僕が如何にそれらとはかけ離れた性格の持ち主であるかは、僕の家族知人は広く知るところです。当時の受け入れのホストファミリーも、現地の友人たちも、後に僕の本来の性格(つまり、物静かとはほど遠い人格)を知ることになります。
さて、ではなぜこの日本から来た若者は物静かだったのか。
簡単な話です。周囲で何が行われているのかが分からなかったのです。英語が聞き取れない。だから何が何だか分からない。ただ、それだけの単純な理由です。
すると何が起こるか、これも自明です。
皆でワイワイやっているところに、一人取り残されて疎外感を感じるようになります。一時は我武者羅に会話に参加しようと試みても、結局分からずじまい。それが繰り返されるうちに、積極的な気持ちも挫けてしまうのです。
そして、「物静かな若者」の一丁上がりです。もちろん、英語を聞き取れるようになるまでのおおよそ3〜4ヶ月の間中、喋りまくる強者もいるでしょう。しかし、多くの留学生は、結果として口を閉ざしてしまう、話しかけられたときだけ口を開く、必要なときだけ話しかけるようになります。
インプットの継続が花開く
 さて、物静かな若者にも、積極的な猛者にも平等に「その時」は訪れます。そうです。英語が聞き取れるようになる日がやってくるのです。
さて、物静かな若者にも、積極的な猛者にも平等に「その時」は訪れます。そうです。英語が聞き取れるようになる日がやってくるのです。
ちなみに僕の場合には、渡米からちょうど4ヶ月を過ぎた頃に「その時」はやってきました。人によってはかなりの差があるようですが、僕の場合には、朝目を覚ましたら、突然英語が「日本語」を耳にしているかのような自然さで語の連続として聞こえて、それどころか頭が勝手にその意味までイメージしてくれるようになったのです。
そして、それを境に物静かな東洋の学生は姿を消して、とても賑やかでワイワイやるのが大好きな本性が姿を現すことになりました。
まずは、これを体験しなくてはいけないのです。つまり、英語を英語のまま日本語に訳すことなく直観的に理解できる英語の回路の構築です。もちろん、そのためには、日々のインプットが大切となります。
留学生であれば、毎日家や学校で英語に触れ続ける。おそらく耳からのインプットは1000時間ほどです。さらに日々課される宿題で10ページ、20ページの英文を読み続ける。これがインプットとなるのです。
余談ですが、留学中は英語の読解に関しても、最初は辞書を片手に格闘していました。しかし、このやり方だといつまで経っても宿題が終わらないので、じきに諦め、辞書にあたらずに読むようにしました。結果として、これが大量のインプットになっていたのでしょう。
さて、ここからアウトプットが始まります。
聞き取れなければ、表面的に音を真似るだけにしか成りません。ミュージシャンたちは耳が良いので真似が上手ですが、いくら歌が上手でも、あくまで真似しているだけで、日本人のリスナーには上手な英語に聞こえることはありますが、実は英語ネイティブにはまったく伝わらない英語で歌っている場合も珍しくありません。
このように真似を通しても英語は身につきません。しかし、一度聞き取れるようになってしまえばこっちのものです。あとは普通に会話しているだけで、相手の話す英語の「音」の特徴が、どんどん頭に入ってくるのです。そして、自分の英語も相手のそれに寄って行きます。
留学生に共通して、彼らが上手に使いこなす英語の発音の代表格は [ɚ] でしょう。[ə] に [ɹ] がくっついた発音で ‘bird, hurt, early’ 等の母音とそれに続くr音の部分です。
続いて [æ][ʌ] などの母音も、見事に使い分けるようになります。念のため例示しておくと [hæt](「帽子」)や [hʌt](「小屋」)の発音です。この2つは、日本語では「ア」にカテゴライズされますが、それが日本語の範疇から抜け出し、別のカテゴリを構築し始めるのです。こうなれば[hɑt](「熱い」)も区別して発音できるようになります。
教わっていないのになぜ分かる?
 留学生たちは、どのようにしてこれらの発音を身につけるのでしょうか。ひとつ間違いないことは、留学先では「発音指導」を受けることは皆無である点です。発音指導どころか、口の動きを教えるような人も、少なくとも僕の留学時代、周囲には一人もいませんでした。
留学生たちは、どのようにしてこれらの発音を身につけるのでしょうか。ひとつ間違いないことは、留学先では「発音指導」を受けることは皆無である点です。発音指導どころか、口の動きを教えるような人も、少なくとも僕の留学時代、周囲には一人もいませんでした。
それでは、どうやって彼らは口や舌の動きを習得するのでしょう。
確かに、[f] [v] [θ] [ð]等の唇を使う子音であれば、口元を見ればそう動いているのが見えるでしょう。また[i] [e] [æ]などの母音であれば、口の開き方に対応しているし、[o] [u] は唇が丸まるので視覚的に識別できないこともありません。もちろん、ナチュラルスピードで話しているので、ひとつひとつの動作をどこまで目視できるかは不明です。また、目視できるとしても、人の口元、特にそれが女の子であれば、彼女らの口元をじっと見つめ続けるなどということを、僕の精神は僕に許してくれませんでした。
ましてや、口の中で行われるその他の子音や母音を創り出す舌の動きは、見ようにも見ることができません。
「幼児は親の口元を見て発音を覚える」などと言われます。確かに、幼児たちは親の口元をしげしげと眺めている時期もあります。
また、マガーク効果(「パ」と言っている映像に「ガ」の音声を合成すると「ダ」に聞こえる)と呼ばれる現象も、ヒトが口の形を見ていることを示しています。そして、言語を使用する際には、聴覚情報、つまり聞き取ったイメージを口の中で再現してみる学習法のみに頼ることなく、視覚情報や顔の表情など、使える情報は何でも使っているのです。
しかし、口元だけでは分からない調音方法は、どのように学んでいくのでしょうか。
そのひとつの答えを、冒頭から述べているヒトの共感する力、モーター理論などから導くことができるのです。
英語圏の幼児たちにしばしば見られる現象として [θ] の発音における [f] の代用が挙げられます。’one two three’ が ‘one two free’ などに置き換えられるわけです。 [f] は上の歯と舌の唇で作る摩擦音で [θ]は歯で作る摩擦音です。つまり、距離が近いので似た音が出るのです。
余談ですが、日本語には [f] の音がありません。従って、日本人の聴覚的に [θ] に近い摩擦音は [s] なので ‘thank you’ が ‘sank you’ などと [s] で代用されるわけです。(これも既述のチャートを見てください)
ちなみに、腹話術師などはこの原理を応用しています。例えば、パ行やバ行を上下の唇の破裂ではなく、舌と上唇を破裂させることで作り出しています。閑話休題。
[θ] を [f] に置き換える。これらの発音は、両方とも口の形に表れます。目に見えて違うのです。それにも関わらず、この置き換えが起こることは、何を意味するのでしょうか。赤ん坊は口の動きも参考にするのでしょうけれども、聴覚イメージ(聞こえた感じ)を自らの口や舌を使って再現していることの、紛れもない証左でしょう。
つまり、英語を聞き取れる耳ができると、モーター理論で言うところの、聞いた音のシミュレーションが行われます。それによって、正しい発音に近づいていくことになるのです。
聴覚イメージから再現する天才なんです
 聞こえた音のイメージを、自分の口で再現してみる。これができるようになるためには、既に触れたように、前提として正しく英語を聞き取れることが必要です。正しく聞き取れていないものを真似しても、正しく発音できないのは言うまでもありません。しかし、正確に聞き取れるようになれば、目をつむってでもそれを再現できる能力をヒトは持っているのです。
聞こえた音のイメージを、自分の口で再現してみる。これができるようになるためには、既に触れたように、前提として正しく英語を聞き取れることが必要です。正しく聞き取れていないものを真似しても、正しく発音できないのは言うまでもありません。しかし、正確に聞き取れるようになれば、目をつむってでもそれを再現できる能力をヒトは持っているのです。
もう幾つか事例を挙げて見ていくことにしましょう。まずは、よくある ‘l r’ の話。いわゆる ‘巻き舌’ で象徴される英語の /r/ の音から始めましょう。
/r/ には少なくとも2つの調音方法があります。1つは ‘bunched r’ でもうひとつが ‘retroflex r’ です。
前者は、舌先から中程にかけて舌の筋肉を盛り上げて、音声の通り道の真ん中に乱流を発生させる発音です。後者は、その名の通り舌を後ろに反らせて発音します。口中の真ん中辺りに乱流が起これば /r/ に聞こえるのですから、どちらでも似た音が生じることになります。
アメリカ人には、この両方の発音が見られ、発音している当の本人たちは、自分がどちらの方法で /r/ を発音しているか、普段考えたこともないでしょうし、言われなければ気付くこともないでしょう。本稿をお読みの方には、英語に自信のある方もいらっしゃることでしょう。是非ともご自身の /r/ がどちらであるのか、一度見極めてみると興味深いかも知れません。
さて、お次は /l/ です。音声学では /l/ は /r/ とともに「接近音」と呼ばれています。 /r/ で触れたように、舌を持ちあげることで上顎と「接近」するのです。結果これらは似ている音になりますが、決定的な違いは /l/ が「側面接近音」である点です。
「面倒な話が始まったな…」とお思いかも知れませんが、難しくないので少しお付き合いください。ここで踏ん張れば「英語の発音が良くなる」ご褒美があります。
/l/ を発音する際に、舌先は歯茎(しけい:歯と歯茎の間)に接触します。舌の先だけでなく、横の部分も上顎に接触させると空気の流れが止まります。やってみてください。するとそれは /t/ の発音です。そうなのです、 /l/ の構えは /t/ とほぼ同じ。違いは /l/ では舌の側面(両側あるいは片方)に空気の逃げ道を開けている点です。
英語の /l/ には ‘dark l’, ‘light l’ の2つの音があると言われています。その状態で /la/ と破裂させて生じる ‘left, list, clap…’ 等に見られる音が ‘light l’ です。
他方、/l/ の構えを保ったまま声帯を動かし続けて得られるのが ‘dark l’ です。こちらは、語の最後などに現れます。
’dark l’ ([ɫ]のような記号で表される)は破裂する /l/ とは明らかに音が異なります。 ‘doll, ball, call…’ 等の語末は [ɫ] となりますが、この音が [u] に近いのです。そして、英語を身につけている最中の子どもたちも、 [ɫ] を [u] で代用することがあります。
お子さんもしているはずですよ。紫を「パーポー」、ワッフルを「ワフォー」、マザーグースの ‘hey diddle, diddle…’ を「ディドディドー」と言うことがあれば、それは ‘dark l’ を模しているのです。
正しく聞き取った上で、正しく再現しようとしている。まさしく「音」の天才ですね。
オマケをつけておきましょう
 ’f, v, th, r, l’ など、上記で述べた音ばかりではありません。それらの組み合わせで複雑怪奇な音が生まれるのですが、子どもたちは(いや留学生や帰国子女、あるいは日本に居ながらにして英語を身につける猛者どもは)それすらもマスターしてしまうのです。
’f, v, th, r, l’ など、上記で述べた音ばかりではありません。それらの組み合わせで複雑怪奇な音が生まれるのですが、子どもたちは(いや留学生や帰国子女、あるいは日本に居ながらにして英語を身につける猛者どもは)それすらもマスターしてしまうのです。
「母音間の叩き音」「鼻腔破裂」「側面開放」等々、専門的な響きのする名前ですが、極めて日常的に行われている調音方法をざっと眺めてみることにしましょう。
まずは「母音間の叩き音」です。これは母音に挟まれた /t/ が日本語の「ラ」あるいは「ダ」の様に聞こえる音の作り方です。 ‘water’ は「ワラー」と言った方が通じるなどと言われるように、確かに通常の速度で話される米語では [tɚ] の代わりに [wɔɾɚ] が自然と生じます。
発音の仕方は至って簡単。この [ɾ] の音は、日本語の「ラ」の音と変わることはありません。連続で「ラララララ」という具合の速度でもって、舌で軽く上顎を叩くと生じる音です。ちなみに [ɚ] は上記の /r/ の舌の構えで、 [ə](「シュワ」) と呼ばれる中立音(口を半開きにして「あー」で出る音)を出すと生じる音です。やってみてください。
次に「側面開放」です。’purple, bubble’ など唇の破裂に ‘darl l’ を後続させたり、’google, buckle’ など「ク」や「グ」の破裂のあとに ‘darl l’ を後続させるのは、少し練習すればできるようになります。しかし、’little diddle’ など /t d/ はその直後に来る ‘darl l’ と舌の位置が同じになるので、少し厄介です。
つまり、歯茎にくっつけた舌を /t d/ の発音のために一度破裂させると、次の ‘darl l’ のためにもう一度舌先を同じ位置に戻さなくてはいけません。これが面倒なのです。そこで、 /t d/ のために歯茎にくっつけた舌の構えはそのままで、舌の両面(あるいは片面)を勢いよく開放して ‘darl l’ の構えにします。すると、「リロー」とか「ディドー」という音になるのです。
最後にもうひとつだけ「鼻腔破裂」を見てお終いにしましょう。’suddenly, kitten’ など ‘t d’ に ‘n’ が後続する音の作り方です。
歯茎から少し後ろにかけての歯茎部は、音を作るのに大変便利な場所のようで、先ほどの /t d/ と同じように /n/ も同じ位置で音が作られます。皆さんは /d/ と /n/ の違いが分かりますか。試しに「ダ」「ナ」と言ってみましょう。何が違うでしょうか。
答えは、軟口蓋にあります。軟口蓋が上がって鼻への空気の流れを止めると「ダ」になり、軟口蓋が下がって鼻への空気の通り道が空いていると「ナ」となります。
軟口蓋を上げたり下げたり…
音声学を学んだことがない限り、そんなことを意識してする人はいないでしょうし、もちろん、自覚もしていません。しかし、1歳の幼児でもこれらの音を分けて発音するのです。驚くべきことですね。
さて、話を戻しましょう。「鼻腔破裂」も「側面開放」と同様に口の中に閉鎖を作る /t/ /d/ の構えをします。その後「側面開放」の様に舌の側面を開放して空気の通り道を作るのではなく、「鼻腔破裂」では、舌の位置は /t/ の構えそのままに、上に持ち上がって鼻への空気の通り道をふさいでいる軟口蓋を瞬間的に下げます。その時いきなり空気が鼻に抜ける破裂音がします。鼻を鳴らすような音です。これが、’suddenly, kitten’ などに見られる音の正体です。
さて、留学生や英語ネイティブの幼児たちは、これらの音をどのようにして自然と身につけたのでしょうか。もう繰り返すことはしませんが、お分かりですね。ヒトは(ちゃんと聞き取れているという前提の上で)周囲で話されている発音を教わることなく、それこそ自律的にシミュレートしながら「寄せて」いく能力を持っているのです。
邪魔をする日本語の知識
 ふとしたときに暗唱を口にする我が子の英語が「英語らしい!」と感じたことのある親御さんは、少なくないでしょう。これは、子どもたちが聞いたままの音を、口の中で調整しながら再現しているからです。そして、特に年齢の低い子どもたちは、英語の発音に対する先行的な知識が無いので、聞いたままを再現できるのです。
ふとしたときに暗唱を口にする我が子の英語が「英語らしい!」と感じたことのある親御さんは、少なくないでしょう。これは、子どもたちが聞いたままの音を、口の中で調整しながら再現しているからです。そして、特に年齢の低い子どもたちは、英語の発音に対する先行的な知識が無いので、聞いたままを再現できるのです。
つまり、彼らは既に英語を聞き取っているからこそ、「としお」や絵本に「寄せた」英語の発音ができるのです。「パルキッズ」、やってて良かったですね。
そして、その後も継続的にインプットを続ければ、英語を英語のまま理解できる回路が作り上げられることは、過去にも繰り返し触れているのでここでは割愛することにしましょう。
それでは、英語を聞き取れるようになったら、あとはひたすら英語を口にすれば正しい発音が身につくのか、というと、なかなかそうは問屋が卸してくれません。
ここまで散々ヒトの音の模写に対する高い能力を述べてきた上で、最後に少しだけ、補足をしておくことにします。
「パルキッズ」にお取り組み中のご家庭でも、我が子の「日本語的な発音」に少し気をくじかれた方もいらっしゃるかも知れません。しかし、これは彼らが日本人である限り、仕方がないことなのです。
それどころか、日本語のアクセントが英語の発話に乗るのは、彼らの日本語の知識がしっかりと形成されている証拠として、歓迎すべきことなのです。
これは、第二言語習得においては避けられないことです。外国語、例えば英語の発音には、程度の差こそあれ必ず母語、つまり日本語の音韻知識が干渉してくるのです。英語と日本語ではリズムが違います。また音節の作られ方が違うのも、英語の発音に大きく影響します。
それら日本語の知識の干渉のうちの、最たるものは「母音挿入」です。
これも繰り返し過去の『パルキッズ通信』で述べているので最小限に留めますが、以下が概略です。日本語では原則として子音の連続や子音で終わることが禁止されています。例えば、’strike’ [straik] では、真ん中の [rai] の部分は日本語で容認されますが、ご覧いただくと分かるように [st] と子音が連続していてさらに [k] と子音で終わっています。
すると、時代によっては ‘sutoraiki, steeki’ のように ‘i’ が挿入されることもありますが、基本的には ‘t d’ を除く子音には ‘u’ が挿入されます。つまり ’sutoraiku’(ストライク)となるわけです。
これは単に発音するときに関わるルールではありません。日本人は英語の音を聞くときに、存在しない母音を聞き取っているのですから、驚きです。
例えば、’spa, skate’ などでは ‘sp’ や ‘ks’ の間に、存在しない ‘u’ を頭の中で創り出して ‘supa, sukeito’ と本来の発音から歪めて聞いているのです。これはかなり英語ができる人にも見られる現象のようで、英語上級者、あるいは帰国子女や留学生でもこのような「幻のu」を英語の単語の中に聞いているのです。
それが幻であろうがなんであろうが、聞いてしまっているのですから、発音するときに自然とそこに寄せていくのは、ある程度仕方がないことでしょう。
念押しをしますが、これは一般的な外国語習得の時に起こることです。『パルキッズ』の子たちは、程度の差こそあれ、中学生以上の学習者よりは遙かに正しく音素を知覚できているので、発音に関しては、心配せずに、彼らの自然に任せてください。下手に矯正することは、英語に対する嫌悪に繋がりかねないので、その点はご注意を。特に、本稿で述べたような内容の発音指導など、くれぐれもお子さんに対して行わないように、お願いいたします。
【編集後記】
今回の記事をご覧になった方におすすめの記事をご紹介いたします。ぜひ下記の記事も併せてご覧ください。
★幼児はメロディで英語を聞き分ける
★英語が身に付く人とそうでない人の決定的な違い
★理解力・思考力・表現力の高い子を育てる簡単な方法
★地頭の良い子の育て方
★英検に合格出来ない理由
【注目書籍】『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)
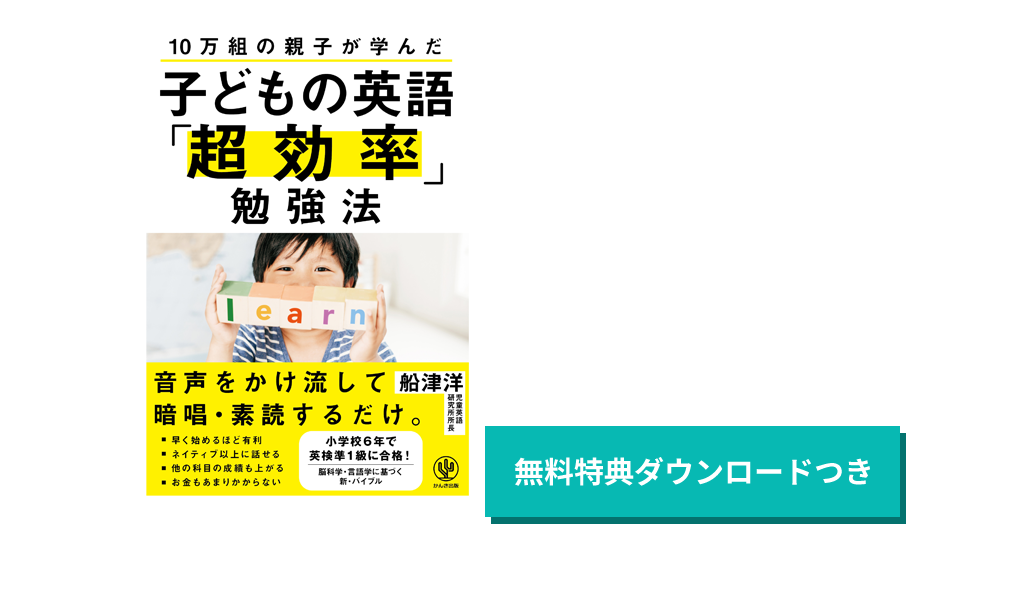 児童英語研究所・所長、船津洋が書き下ろした『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)でご紹介しているパルキッズプログラムは、誕生してから30年、10万組の親子が実践し成果を出してきた「超効率」勉強法です。書籍でご紹介しているメソッドと教材で、私たちと一緒にお子様をバイリンガルに育てましょう。
児童英語研究所・所長、船津洋が書き下ろした『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)でご紹介しているパルキッズプログラムは、誕生してから30年、10万組の親子が実践し成果を出してきた「超効率」勉強法です。書籍でご紹介しているメソッドと教材で、私たちと一緒にお子様をバイリンガルに育てましょう。


船津 洋(Funatsu Hiroshi)
株式会社児童英語研究所 代表、言語学者。上智大学言語科学研究科言語学専攻修士。幼児英語教材「パルキッズ」をはじめ多数の教材制作・開発を行う。これまでの教務指導件数は6万件を越える。卒業生は難関校に多数合格、中学生で英検1級に合格するなど高い成果を上げている。大人向け英語学習本としてベストセラーとなった『たった80単語!読むだけで英語脳になる本』(三笠書房)など著書多数。