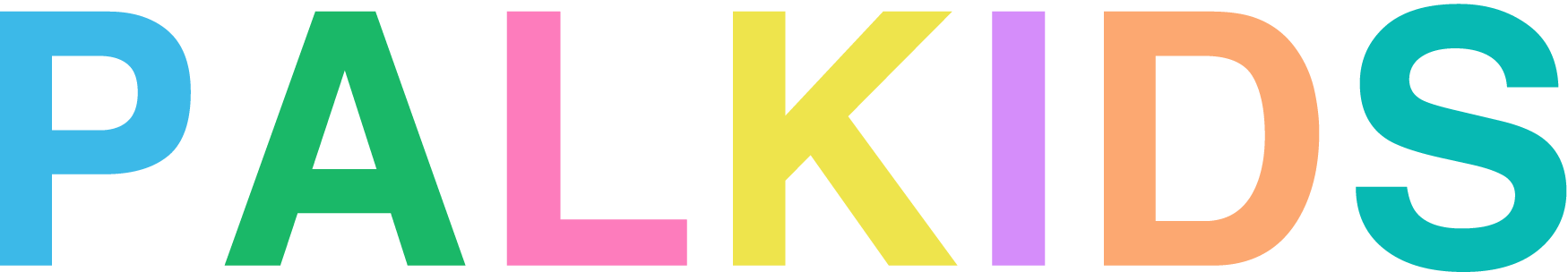パルキッズ通信 特集 | かけ流し, 大量インプット, 英語教育, 言語学, 言語獲得
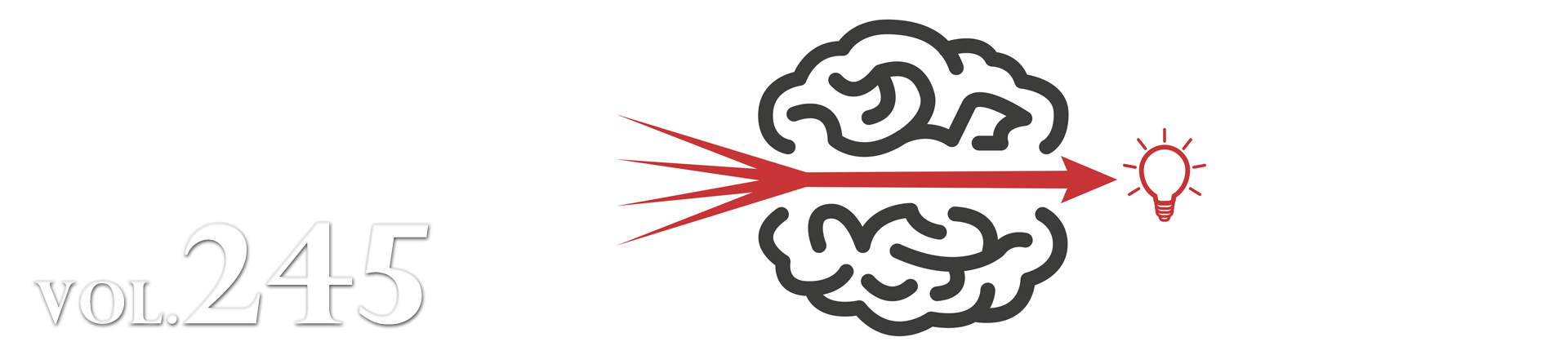
2018年8月号特集
Vol.245 | 英語が身に付く人とそうでない人の決定的な違い
「やる気」と「楽しさ」に頼る人が陥る「入力不足」
written by 船津 洋(Hiroshi Funatsu)
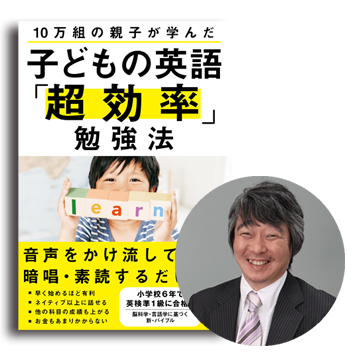
船津 洋(Funatsu Hiroshi)
1965年生まれ。東京都出身。株式会社児童英語研究所・代表取締役。上智大学外国語学部英語学科卒業後、言語学の研究者として、日本人の英語習得の在り方を研究中。35年以上、幼児・児童向け英語教材開発の通して英語教育に携わる経営者である一方、3児の父、そして孫1人を持つ親として、保護者の視点に立ったバイリンガル教育コンテンツを発信し、支持を得ている。著書に20万部のベストセラーを記録した『たった80単語「読むだけで」英語脳になる本』(三笠書房)をはじめ『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)など多数ある。
| 「臨界期仮説」を否定する「入力仮説」
 先日、言語学者のフレゲ博士(Dr. James Emil Flege)の『臨界期仮説が英語学習者のアクセントと分節音産出の正確な予測に失敗』と題する講話があり、時間があったので参加してきました。1時間程の短いお話しだったのですが、いろいろと参考になったので、今回はそれに関連して書いてみたいと思います。タイトルを見てもなんだか分からないかと思いますが、ざっと内容をかみ砕くと、以下のような内容です。
先日、言語学者のフレゲ博士(Dr. James Emil Flege)の『臨界期仮説が英語学習者のアクセントと分節音産出の正確な予測に失敗』と題する講話があり、時間があったので参加してきました。1時間程の短いお話しだったのですが、いろいろと参考になったので、今回はそれに関連して書いてみたいと思います。タイトルを見てもなんだか分からないかと思いますが、ざっと内容をかみ砕くと、以下のような内容です。
前提となっているのは、1967年にレネバーグ(Lenneberg)さんという神経学者兼言語学者が母語の獲得に関して立てた「臨界期仮説」というもので、幼児期に人間の社会から離れて過ごした子や、聴覚障害が放置されたケースなどで「ある年齢(臨界期)を過ぎると、母語の獲得が困難になる」とする仮説です。母語に関しては、どなたも納得するところでしょうけれども、この仮説は母語のみではなく、第二言語習得にも言及していることから、いろいろと議論を呼んでいます。
臨界期の存在は、「移民の家族の英語力」を例に取って導き出されます。米国移民で、移住時にすでに大人になっている人は、ナチュラルなレベルまでの言語(英語)習得が困難な一方で、子どもはそれが可能であることから、思春期前後に臨界期が存在すると想定されています。これに対して、フレゲ博士が「臨界期ではなく受けとる入力の量が異なることで、言語の習得の可否が左右される」と一部反論している形で上記のタイトルで話をされていたわけです。
結論から言ってしまえば、外国語習得には臨界期は存在せず、入力の質と量がその習得を成否を左右するというものでした。フレゲ博士の実験では、イタリアから米国への移民、数百名単位について、英語のアクセントの有無と母音の発音の正確さを、英語のネイティブ話者に判断させるという手法が採られています。13才以前とそれ以降の年齢に渡米した被験者の英語力の差、つまり臨界期以前と臨界期以降のそれぞれに、英語の習得を果たした人たちの英語力を比較する形で行われたわけです。
結果として、臨界期以前に渡米した若年層グループの方が総じてネイティブと紛う英語力を身につけていて、臨界期以降のグループの英語はネイティブのそれでは無いと判断される傾向にあることは間違いありませんでした。やはり臨界期仮説は正しいのか、という結果です。
ところが、フレゲ博士は新しい発見をします。思春期を過ぎて、つまり外国語習得の臨界期を超えているにもかかわらず、臨界期以前に渡米した子と同様に、ネイティブ並の英語力を身につけているグループがあったのです。(また逆に、臨界期以前に渡米したにもかかわらず、臨界期以降の学習者と同じようなレベルの英語力に留まるグループもありました。)要するに、臨界期説の否定証拠が出てきたわけです。言い換えれば、外国語習得に臨界期は存在しない、という実例があったわけです。そして、繰り返しになりますが、フレゲ博士は彼らの英語力の差を「英語の入力」の差に帰しています。
| 男女で違う?
 学習開始の年齢ではなく「入力」の差が、英語を身につけられるか否かの差であるとは、とても興味深い指摘です。クール(Patricia K. Kuhl)さんの「幼児の音素学習云々」の実験結果からしばしば引用される「日本人の幼児は11ヶ月を過ぎると/l, r/ の聞き分けをしなくなる」なども、臨界期仮説と相通ずる、日本人が英語ができない理由のひとつとして挙げられたりしますが、フレゲ博士の仮説は、直接ではありませんが、それに「ちょっと待った」をかけたわけです。それはそうです。11ヶ月を過ぎてから英語を獲得する日本人幼児は少なからず存在しますし、幼児期どころか、臨界期を超えてから英語を身につける人たちも確実に存在するのですから。他方で、当然のことながら、英語を身につけられない日本人は無数にいます。フレゲ博士によれば、できる人とできない人を隔てるのは「臨界期」ではなく「入力の差」だというわけですから、これは、日本人の英語学習者にとっては朗報でしょう。
学習開始の年齢ではなく「入力」の差が、英語を身につけられるか否かの差であるとは、とても興味深い指摘です。クール(Patricia K. Kuhl)さんの「幼児の音素学習云々」の実験結果からしばしば引用される「日本人の幼児は11ヶ月を過ぎると/l, r/ の聞き分けをしなくなる」なども、臨界期仮説と相通ずる、日本人が英語ができない理由のひとつとして挙げられたりしますが、フレゲ博士の仮説は、直接ではありませんが、それに「ちょっと待った」をかけたわけです。それはそうです。11ヶ月を過ぎてから英語を獲得する日本人幼児は少なからず存在しますし、幼児期どころか、臨界期を超えてから英語を身につける人たちも確実に存在するのですから。他方で、当然のことながら、英語を身につけられない日本人は無数にいます。フレゲ博士によれば、できる人とできない人を隔てるのは「臨界期」ではなく「入力の差」だというわけですから、これは、日本人の英語学習者にとっては朗報でしょう。
まず、「臨界期仮説」では、臨界期は思春期と仮定されています。神経学面での成長に伴い、思春期辺りでもはや第一言語の獲得の能力は激減し、第二言語獲得も困難になるそうなのです。この点に関して、フレゲ氏は彼らが社会環境の中で受けとる「入力」の差であると指摘しています。学齢期の子どもたちは、成人と比べて遙かに良質の、さらに大量のネイティブによる英語の発音に晒されます。それが入力となる、というわけです。逆に大人になると、社会生活を営むために、必要に応じて英語を使いますが、学校に通っている子どもたちに比べれば、その入力量は足下にも及ばないのは想像に難くありません。ゆえに、子どもの方が英語の獲得に有利な条件を揃えているということです。良質の入力が多いから、ネイティブ並の英語が身につくのです。
また、/l, r/ の聞き取りができない日本人に関しても、フレゲ氏は「絶対的に入力が足りない」と仰っていました。少し考えてみれば分かることです。アメリカ人の赤ん坊が英語を身につけるまでに、一体全体どれだけの量の/l, r/の発音を耳にしているのか。それに比べて日本人は入力をまるで受けとっていないに等しいわけです。つまり「入力」がないのだから、聞き取れないと言って悲しむ必要はない。臨界期だから聞き取れないのではなく、入力の量に問題がある。そんなロジックが展開されます。
また、フレゲ博士のこの研究では、とても興味深いいくつかの考察が為されています。なんと、性別で英語の獲得に差が出るというのです。学齢期に米国に来た子どもたちでは、女の子の方が男の子よりも英語へ対応が早いそうなのです。パルキッズユーザーを見ても、我が子を振り返っても、言語に敏感でより才能を発揮するのは、大抵女の子。男の子は総じてことばの成長がゆっくりです。ところが、大人になるとこれが逆転するそうなのです。大人になってからの移民のケースでは、男性の方が女性よりも英語に対する対応が早く行われる。これに関しても、教授は「入力」の差だと結論づけています。つまり、そもそも経済的な理由でアメリカに移住するわけですから、経済活動を行わなければいけないのは当然です。その結果、主に外で仕事をする男性の方が、家庭にいる女性よりも英語を使う頻度が高くなる。ゆえに、成人の場合には男性の方が女性よりも早く、より英語らしい英語を身につけるというのです。これも、言われてみれば、納得できます。
| 英語を「教える」教授法における「入力量」
 さて、日本人の英語下手ですが、これを日本人のシャイな性格、日本語と英語の言語間の差異、学習開始年齢、はたまた教授法など、様々な原因に帰することが行われていますが、今回はフレゲ博士に倣って、すべてを「入力の差」という点から検証し直してみることにしましょう。言語習得と「入力」の面に関しては、クラッシェン(Stephen Krashen)という言語学博士が「入力仮説」とか「獲得・学習仮説」などというものを立てて、第二言語教育の場では広く活用されているので、そのあたりも絡めながら、考えて参ります。
さて、日本人の英語下手ですが、これを日本人のシャイな性格、日本語と英語の言語間の差異、学習開始年齢、はたまた教授法など、様々な原因に帰することが行われていますが、今回はフレゲ博士に倣って、すべてを「入力の差」という点から検証し直してみることにしましょう。言語習得と「入力」の面に関しては、クラッシェン(Stephen Krashen)という言語学博士が「入力仮説」とか「獲得・学習仮説」などというものを立てて、第二言語教育の場では広く活用されているので、そのあたりも絡めながら、考えて参ります。
英語教授法の第一は、「教授法」と呼ぶくらいですので、先生が生徒に「教える」方式で行われるものです。この教授法はクラッシェン博士の「獲得・学習仮説」と「モニター仮説」で説明すると分かりやすいので、簡単にご紹介します。(これらに関しては『パルキッズ通信2016年1月号』で書いているので詳しくはそちらをご参照ください。)
「獲得・学習仮説」では「言語の獲得と学習とは2つの異なる心理活動で、獲得とは幼児が母語を身につけるような方法、学習とは言語自体を身につけるのではなく、言語に関する知識を身につけること」だと言います。獲得とは無意識に属する脳の活動で、学習とは意識的な活動であると言い換えられます。学習の延長に獲得があるのではなく、それぞれ別の脳内活動ということです。そして、外国語を身につけるためには、学習ではなく獲得が重要であるとするスタンスをとっています。
これに関して「モニター仮説」というものも立てられています。「モニター仮説」によれば、学習して得られた知識は獲得に当たってのモニターの役割を果たすというものです。英文を作ろうとする時に、文法知識に照らしあわせる(モニター)ことからこのように呼ばれています。察するに、英文を日本語に訳したりする時にも文法に照らし合わせているので、この点も含まれると想像します。
これは『パルキッズ通信2013年7月号』で触れたところの、100年以上も前に夏目漱石先生が学生達に勧めた学習法で、「初級の文法を修めた者は大量に読めば良い、云々」と通底します。洋の東西を問わず、同じような学習にたどり着く人たちはいるのですね。
さて、日本での「教授法」ですが、学習の方ばかり取り組んでいることがわかります。最近では大学入試でもあまり問われなくなってきた、重箱の隅をつつくような文法教育に、未だに拘泥している教授法もあるようです。このような学習法(つまり獲得でなく学習)の先に「英語の獲得」が存在しないことは、クラッシェン博士ならずとも、ほとんどの日本人が身を以て体験してきたのです。学習者が意欲的に多読にでも取り組んで、大量の入力をするのであれば話は別ですが、従来的な文法教育、つまり「入力」が決定的に足りない「教える」方式で英語が身につくことはないでしょう。
| 英語を「楽しむ」学習法における「入力量」
 まさか幼児とか小学校低学年の子どもたちに、英文法や対訳付きの英単語を教え込もうと考える人は少ないでしょう。そんなことをしたら、せっかく幼児たちが持って生まれた言語に対して極めて優秀な吸収力を持つ脳に、大人たちが失敗した「学習」をさせることになってしまいます。しかも、子どもたちにはまだロジックが分からないので、文法など理解できないのです。幼児期にこそ直感的な「獲得」を目指したいと思うのは自然でしょう。そして、そんな幼児たちに対する英語教育としては、英語を「楽しませながら」身につけさせようといった風潮が少なからず見受けられます。それどころか、「楽しませる」方式が幼児教育では本流かもしれません。では、この楽しみながら英語を身につけるという考え方は「入力」面から見るとどうなのでしょう。英語を身につけるに足る、十分な入力が担保できるのでしょうか。
まさか幼児とか小学校低学年の子どもたちに、英文法や対訳付きの英単語を教え込もうと考える人は少ないでしょう。そんなことをしたら、せっかく幼児たちが持って生まれた言語に対して極めて優秀な吸収力を持つ脳に、大人たちが失敗した「学習」をさせることになってしまいます。しかも、子どもたちにはまだロジックが分からないので、文法など理解できないのです。幼児期にこそ直感的な「獲得」を目指したいと思うのは自然でしょう。そして、そんな幼児たちに対する英語教育としては、英語を「楽しませながら」身につけさせようといった風潮が少なからず見受けられます。それどころか、「楽しませる」方式が幼児教育では本流かもしれません。では、この楽しみながら英語を身につけるという考え方は「入力」面から見るとどうなのでしょう。英語を身につけるに足る、十分な入力が担保できるのでしょうか。
ここで再びクラッシェン博士にご登場いただき、今度は「入力仮説」をご紹介しましょう。この「入力仮説」では「理解しうる情報+1」を与え続けることが重要であると説いています。そして、「理解しうる情報+1」が「理解しうる情報」になったら、今度はそれに「+1」をして、どんどんインプットを増やしていき、それにより言語の獲得が可能になる、という考え方です。
子どもたちが母語を身につける過程を振り返ってみると、明らかな点がいくつかあります。子どもたちが受けとる言語のインプットには、1)「繰り返し」があるということ、また一定量以上の 2)「大量さ」がある点、さらに、同じ情報ばかりでなく、常に3)「新しい」情報が入力される点です。これらの点において、入力仮説は幼児が母語を獲得する環境の中にある言語のインプットの一面を表しているといえます。
さて、件の「楽しむ」という点に関してですが、楽しい英語とは何でしょうか。キャラクターもののストーリーはもちろん楽しいでしょうし、ドラマなどストーリー性の高いもの、ミュージカルなものなど、子どもたちの興味を引くものは数多ありますので、子どもたちは楽しみながらそれらを視聴するはずです。楽しければ積極的に繰り返し視聴することでしょう。ところで、そのような映像コンテンツを、子どもたちは何回繰り返し見てくれるでしょうか。10回でしょうか?20回でしょうか?おそらく、どんな楽しいコンテンツも、20回も見たら飽きてしまうのではないでしょうか。そして一度飽きてしまえば、もう観てくれません。つまり、入力はそこでストップです。「入力」が確保できなければ、英語の獲得はそこで止まってしまうことになります。そして、また別の楽しい映像コンテンツを探すことになります。英語の獲得には、少なくとも2〜3年の時間が必要であることを考えれば、飽きたら別のもの、また飽きたら別のものという形で、教材から教材へと渡り歩くことになります。
また、映像コンテンツは視覚情報に頼る分、音声情報としては驚くほど少ないことが珍しくありません。子ども向けのアニメを音だけ聞いてみると、音声と言うよりは効果音ばかりが耳に付きます。時間の割には非効率な入力で、それを大量に与えるとなるとビデオ漬けにすることになるので、目にも脳にも良くないことは、言うまでもありません。
それでは、楽しい英語教室はどうでしょう。もちろん、大いに活用すれば結構ですし、後述しますがそれが「モチベーション」につながるならば、大歓迎です。その反面、場所や時間に制限があります。ずっと教室に入れっ放しにしておくのであれば話は別ですが、週に1〜2度、数時間程度では、圧倒的に入力量が少ないことは明らかです。その点では、教室などのレッスンも映像コンテントと同様で、「入力量」において言語獲得を満足させるような量を提供してくれません。
獲得に必要な入力量を担保するには、MP3音源などのかけ流しで、環境に英語の音声を存在させることが効率が良いと考えられます。また、映像はどうしても積極的な視聴なので、意識した学習になりがちなのに対して、MP3などの音源のかけ流しは無意識の学習へとつながるのがメリットです。前出のクラッシェン博士の「獲得・学習仮説」に照らし合わせても、英語の獲得を促すためには、音声での無意識の入力が効果的と言えるのです。
つまり、楽しければ入力量が増えるのかといえば、必ずしもそうではないのです。映像コンテンツやレッスンは楽しいものですが、継続的に入力するツールとして適しているとは言えません。どちらかと言えば、出力を促す取り組みです。映像やレッスンは出力の取り組みとして活用する一方、英語を身につけるためには、どこかで入力を確保する必要があるのです。
| モチベーションアップと「入力量」の関係
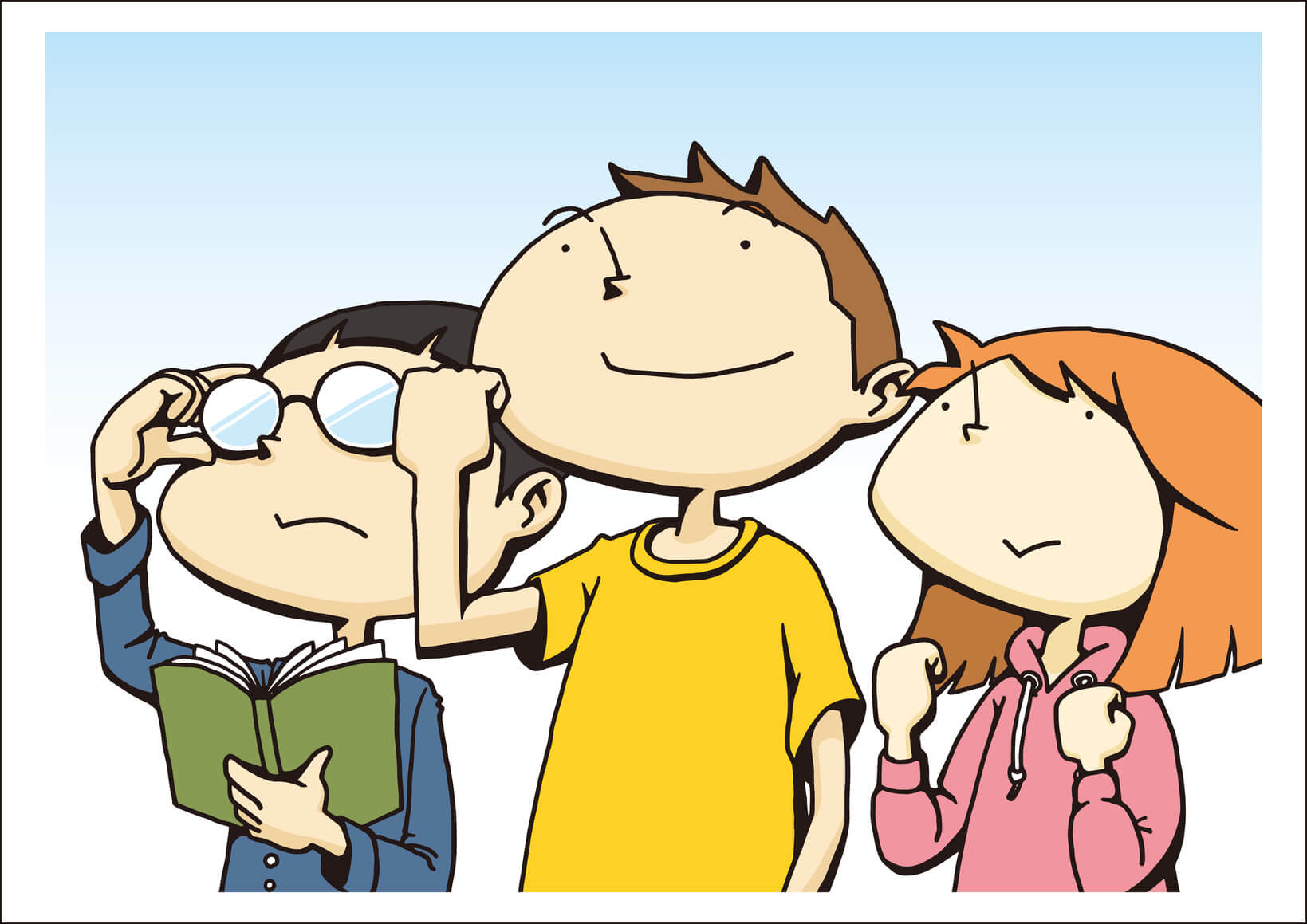 外国語習得に限ったことではありませんが、学習に関してことある毎に持ち出されるのが「モチベーション」とか「やる気」などの概念です。また、意欲的な学習や積極的な学習という意味で、最近いろいろなところで耳にするCLILなども、前述の「楽しく」取り組める学習方法のひとつと言えます。CLILに関しては『パルキッズ通信2018年3月号』で紹介しているので、そちらをご参照いただくとして、モチベーションややる気、積極性などは英語習得にどのような影響を与えるのでしょうか。
外国語習得に限ったことではありませんが、学習に関してことある毎に持ち出されるのが「モチベーション」とか「やる気」などの概念です。また、意欲的な学習や積極的な学習という意味で、最近いろいろなところで耳にするCLILなども、前述の「楽しく」取り組める学習方法のひとつと言えます。CLILに関しては『パルキッズ通信2018年3月号』で紹介しているので、そちらをご参照いただくとして、モチベーションややる気、積極性などは英語習得にどのような影響を与えるのでしょうか。
一般的に考えて、何事も「やる気」があるに越したことはありません。しかし「やる気」とは一体何なのでしょう。「積極性」や「やる気」があると、なぜ学習効果が高くなるのでしょうか。これに関しては専門家ではありませんが、あくまでも常識の範囲の中で考えてみると、やる気があってやり始めると集中できるということがあります。集中しながら取り組むのと、集中せずに取り組むのでは、これは集中して取り組んだ方が良いに決まっています。では、なぜ集中して取り組むと良いのでしょう。これもやはり「入力」と関係がありそうです。
フレゲ先生が、講話で少しだけ触れていました。「やる気は数値化できない」しかし「やる気があるということは、結果として入力量が増えることにつながる」。つまり、「やる気は大量の入力への窓である」とのこと。言われてみれば、確かにそうです。これを先ほどの話と繋げると、やる気は取り組み開始への鍵であり、取り組みを開始して集中できれば、つまりは入力量が増えることになるのではないでしょうか。やる気があるから学習効果が高いのではなく、入力が増えるから学習効果が高いと言えそうです。
さて、ここに関して、またクラッシェンさんの「入力仮説」を引っ張り出すと、「理解しうる情報+1」が大切であることが再確認されます。やる気を出したとして、取り組みを開始したとしても、「理解不能の情報」に接してしまったら、取り組みに集中できずに、結局中断、入力もストップします。あくまでもやる気を継続するためには「理解しうる情報+1」の入力が大切です。
さらに、「やる気」の継続 (=「入力量」の増加) に影響する「情意フィルター仮説(Affective Filter Hypothesis)」をクラッシェンの理論からを紹介しておきましょう。この仮説では、既述したところのやる気、または自信などはポジティブな効果を学習に及ぼし、逆に恐怖や困惑などはネガティブな効果を与えるというものです。怒られたり、怒鳴られたり、強制されたりすると学習が進まなくなるそうです。もし身に覚えがあれば、改めた方が良さそうですね。
ところで、やる気などが入力量の向上につながることは分かりましたが、そもそも入力量が増えれば学習効果が高いというのは、常に真実なのでしょうか。ここまで書いておいて「今さら何を」と感じるかも知れませんが、何事も疑ってかかるのが賢明ですので、入力の量の単なる増加が学習効果に直結するのかどうか、考えてみることにします。なぜこの点に疑義を挟むのかというと、日本人ミュージシャンの中で、英語の発音がどうにもまずい人があまりに多いからです。ミュージシャンといえば、おそらく人一倍音楽を耳にし続けてきているはずです。洋楽も、それこそ四六時中聞いているのではないでしょうか。洋楽といっても無限ではありませんし、それぞれの好みもあるでしょう。すると、同じような内容をそれこそ無限に聞き続けている、つまり入力し続けているはずです。それにも関わらず、英語の発音がお粗末な音楽家がたくさんいるのです。
| 入力の方法
 なぜ人一倍洋楽などを通して英語を耳にしているはずの音楽家たちの英語の発音が悪い、などということが起こるのでしょう。この言い方は少し意地悪が過ぎるかも知れませんので、彼らを擁護するために付け加えておくと、発音が悪い音楽家でも、世間一般と比べれば、余程英語の発音は良いのでしょう。ただ、英語ネイティブの耳にはネイティブの発音として届かないだけのことです。つまり、洋楽などを毎日耳にすることで、それをしない人よりは英語の発音がよくなることはあるのでしょう。
なぜ人一倍洋楽などを通して英語を耳にしているはずの音楽家たちの英語の発音が悪い、などということが起こるのでしょう。この言い方は少し意地悪が過ぎるかも知れませんので、彼らを擁護するために付け加えておくと、発音が悪い音楽家でも、世間一般と比べれば、余程英語の発音は良いのでしょう。ただ、英語ネイティブの耳にはネイティブの発音として届かないだけのことです。つまり、洋楽などを毎日耳にすることで、それをしない人よりは英語の発音がよくなることはあるのでしょう。
しかし、彼らの英語がネイティブにほど遠いのは現実です。では、なぜ聞いているだけでは英語の発音は改善されないのでしょうか。おそらく、それは彼らが英語の音素の知識なしにリスニングに臨んでいるからでしょう。クラッシェン風に言えば、彼らにとっての洋楽は「理解しうる情報+1」ではないのかもしれません。これは詞の内容という側面ではなく、英語の音素という側面においてです。
この点に関しては、自身も体験したことなので、少し触れておきます。僕にとっての英語といえば、英語(British English)ではなく米語(American English)のことでした。留学したのも米国のみですし、僕の発音も GA(General American)と呼ばれる典型的な米国の標準アクセントです。他に英語圏といえば、数度ニュージーランドを訪れたことがある程度ですが、もちろん、米語のみでなく英語も聞き取れます。しかし、英語といっても様々で、RP(Received Pronunciation)は問題なく聞き取れますが、北部のスコットランド訛りやアイルランドに近いリバプールやマンチェスター、中西部のウェールズの訛りなどは、映画を見ていても辟易とするほど分かりませんでした。同じ英語とは思えないほど発音の仕方が違うのです。
ところが、たまたまそれらの訛りを分析した文献に接する機会があり、それぞれの訛りの特長を体系的に知ることができました。するとどうでしょう。分からなかった英国訛りが聞き取れるようになったのです。50才を過ぎての出来事です。「臨界期仮説」はやはり、僕の体験によっても疑義が挟まれたかたちです。
ところで、このエピソードの中で重要なのは、音素の知識の有無が聞き取りに影響する点です。英国北部の訛りの音声的特長を知らないうちは聞き取れない。しかし、一度知ってしまえば、すっと頭に入ってくるのです。つまり、それまでは入力されなかった英国式アクセントが、音声の知識を得ることで問題なく入力されるようになったのです。やはり「理解しうる情報」が入力されるのでしょう。音楽家の皆様におかれましては、いや、音楽家に限らず英語を学習する皆様においては、たった26文字、40程度しか存在しない英語の音をキチンと勉強されることをお勧めします。音素を知るだけで、英語は「理解しうる情報」となるのですから、これをしない手はないでしょう。
| 入力の質
 ここまで、主に入力の「量」に焦点を当てて書いてきましたが、実は入力の「質」も大きな鍵を握っています。ただ、紙数も尽きてきましたので、簡潔に触れて終わりにしたいと思います。
ここまで、主に入力の「量」に焦点を当てて書いてきましたが、実は入力の「質」も大きな鍵を握っています。ただ、紙数も尽きてきましたので、簡潔に触れて終わりにしたいと思います。
フレゲ先生の講話の中で、いわゆる「臨界期」前にイタリアから米国に到着した若年層の中で、最後までイタリア語訛りが消えなかったグループがあります。成人してからでも、良質の英語に大量に触れ続けることによって、ネイティブと紛う発音を身につけられた一方で、若年にして米国へ渡る機会を得ながら、その環境をフルに活用できなかった人たちです。
そんな人たちがどんなグループであったか?という質問に、フレゲ教授は「イタリア語訛りの英語を耳にする機会が多かったためではないか」と答えています。イタリア系移民で固まってしまう環境に属していたり、例えば、親がイタリア料理店などを経営していて、それを手伝うとなると、イタリア語やイタリア語訛りの英語の入力がふんだんにあるため、それが「入力」となってしまったのではないか、ということです。つまり、「入力の質に問題があった」ため、正しい英語を身につけられなかったと結論づけているのです。
最近でもたまに目にしますが、日本人の母親が日本人の我が子に、日本語交じりのカタカナ英語で話しかけていることがあります。『パルキッズ』の学習では、誘い水程度に親が英語を話すことを勧めてはいますが、英語が苦手である場合には、一切英語を話す必要はない、とご指導差し上げています。良かれと思ってしていることが、結果として「良質」ではない英語の入力となってしまう恐れがあるからです。
さて、長々と英語習得(主に発音)と、英語の入力量とその質に関して触れて参りましたが、『パルキッズ』をお使いいただいているご家庭におかれましては、現状を何も変更する必要はございません。『パルキッズ』では入力用の音源と同時に、オンラインレッスンが出力の「誘い水」となるような構成ですので、淡々と取り組むだけで出入力共に満足できる教育が可能です。順調に進んでいるご家庭はその調子で、うまく行っていないご家庭でも、夏休みを積極的に活用して再スタートするなど、「入力」だけは続けるようにしましょう。
*参考文献
『Effects of age of second-language learning on the production of English consonants』
『Foreign-language experience in infancy: Effects of short-term exposure and social interaction on phonetic learning』
『Stephen Krashen’s Theory of Second Language Acquisition』
次の記事「パルキッズのかけ流しの取り組みで勘違いをしていませんか?」
次の記事
パルキッズのかけ流しの取り組みで勘違いをしていませんか?
※本記事のテキストは引用・転載可能です。引用・転載する場合は出典として下記の情報を併記してください。
引用・転載元:
https://www.palkids.co.jp/palkids-webmagazine/tokushu-1808/
船津洋「英語が身に付く人とそうでない人の決定的な違い」(株式会社 児童英語研究所、2018年)